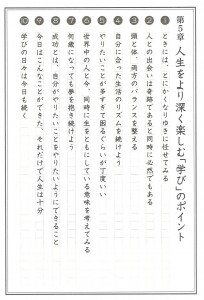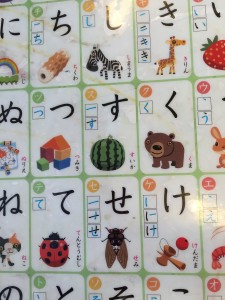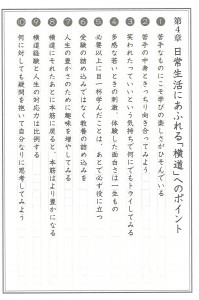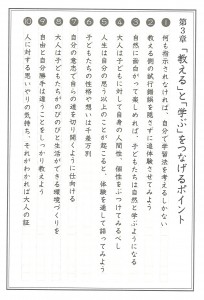とうとう最後の章となりました。そもそも私がこの本を購入したのは今から約3年前で、この本が出版された年です。たまたまテレビを見ている時に橋本先生の特集をしていて、見ていると共感できることが多く、それこそ「見守る保育」じゃないか!と思い、本屋に走り購入したのです。ただ、ここで注意していただきたいのでは、橋本先生の教えを学ぶといよりも、私はなぜこういう考え方になるのだろう?と気になったのです。
今まで読んで下さった方も感じていると思いますが、塾長が普段から言われている言葉や見守る保育の理論と共通部分が多々ありました。さらに橋本先生は高校教師でしたので、見守る保育がいかに幼児教育だけでなく、高校でも成り立つという結論にも注目してみたいと、思ったのです。高校になると授業もかなり難しくなりますし、何よりも大学入試という大きな壁があります。それらをどう乗り越えていくのか、など参考になるのでは?と思いました。
さて、最後の章ですが、ここでは橋本先生の人生について書かれてありました。その中で個人的に面白かったのは 「なりゆきに任せる生き方」 と言うことです。言われるがまま、なるようになる、といったように時の流れに自然に寄り添うということが実に多かったそうです。ただ、自分で決めなければいけない場合は自ら選択し、決断してきたそうですが、おそらく橋本先生の選択が良かったのだと思います。それこそ塾長がよく塾生にも言われますが「優先順位を間違えてはいけない」という事と同じではないでしょうか。
さらに橋本先生は「好きなことを好きなだけやる」これも心構えとして持っていたようです。
おそらく橋本先生は教師という職業を仕事として捉えているのでなく、趣味として捉えていたのではないでしょうか。そのへんも塾長は「私の趣味は仕事です」と講演でも同じ様な事を言われています。私も今は趣味は仕事ですと自信を持って言えます。これは個人的主観になってしまうのですが、私が塾長の助手として出張に行っていたときに
「山下くん、もし『仕事』として出張に来ているならば、来なくていいよ」
その言葉を言われて目が覚めた思い出があります。かと言って出張を趣味として捉えるのも何だかおかしいですよね(笑)助手として行くのは、もちろん塾長をサポートする役割もありますが、何よりも一緒に楽しく、そして学ぼうという意欲が当時の私には足りなかったのかもしれません。それを感じ取った塾長は私にそのような言葉をかけたのだと思います。そこから私も考え方が変わったのを思い出しました。
今週の塾でこんな話が出ました。少し報告と重なってしまうので深く言いませんが、
「子ども達が大きくなって、何かのときに『あれ?これはどこかで誰かに教わったような・・・』と感じた時に、その『誰か』になりたい。」
すごく深い言葉です。私もこの言葉を聞いたのは講演ではなく、二人で話しをしているときに聞いた気がします。橋本先生も「スローリーディング」の事が記事に取り上げられたとき教え子の一人が橋本先生に手紙を書いたそうです。その生徒とは卒業してから40年ぶりのやり取りだったそうで、それを受け取った橋本先生は「教え子の心に残っているということは、最高の喜びであり、教師冥利です」と書いています。若干、塾長と状況は違いますが、これぞ学びだと私は思います。
塾長と出会ってからまだ10年も経過していませんが、それでもたくさんの事を学びました。色々な状況なときに、こんなときに塾長はこういうことを言っていたな、こういう考え方をしていたな、と感じ取れるようになりました。また自然と行動に出ていることも時々あります。
確か、このホームページを始めた時に私が本当の学びは師の考え方を学ぶと書いた記憶があります。塾長の教えを頭で覚えるのでなく、体全体で感じ取り、そして習慣として身につけ、それこそ塾長の言葉行動、考え方が自然と言葉や行動して表れることが本当の学びだと思います。
それが塾長の冥利なのかもしれません。
最後になりますが、塾長と橋本先生は同じ教育者として言動が似ている事がありブログに紹介しましたが、一番の共通項は
「自分の活躍ではなく、教え子の活躍を何よりも喜ぶ」
これだと思いました(報告者 山下祐)