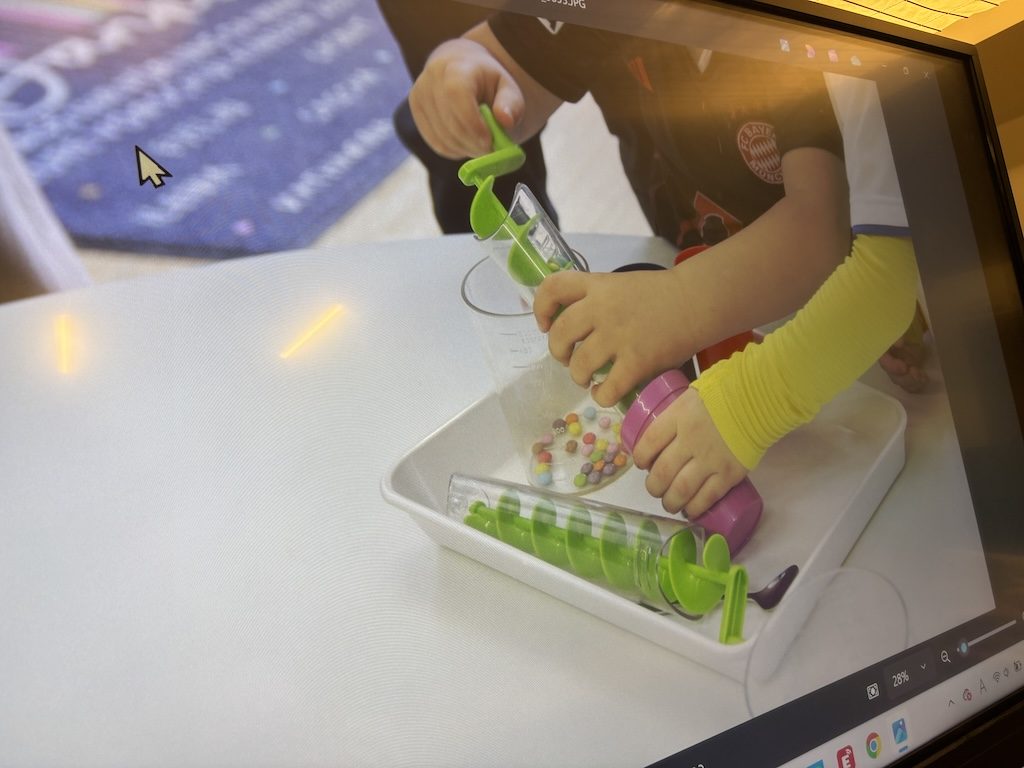2月20日の塾報告をさせていただきます!
遅くなってしまい大変申し訳なく思っております…
この日は次世代セミナーがあり、東京に来ていた外部臥竜塾生の西村氏も参加して開催されました。

そして開催場所はこちらになります!
とても美味しい料理をいただき塾生一同大満足でした!

いつも美味しい料理をありがとうございます!

なんだか久しぶりにこうした会に参加することができ嬉しく思います。

なかなか話が会の内容までいきませんが正直内容はなかなかうる覚えです笑
しかしながら、とても印象的だった内容をここに記したいと思います。

右に写っている伊藤カレラ先生(見切れててすいません)が新人で今年度から就職され、来年度は1歳児クラスを担当されるということで私に連絡帳の書き方を教えて貰えますか?という質問が以前ありました。
私はなかなか感覚で生きているため、「端的に書いてお子さんの姿が親御さんに伝わってもらえたらいいと思うよと…」なんて説明不足。こんなアドバイスしかしてあげられなかったです。最近は我が子も(二人目の子ども)久しぶりに保育園に通い始め、先生方の連絡帳を拝見し、感銘を受け身が引き締まる思いでいるため、書き方を考えようと思っています。
そんな話はどうでもよく、ワインを飲んでいる廣田先生にもカレラ先生が聞いたところとてもカッコ良いアドバイスをいただいていました。
「親御さんとの信頼関係も大事で書ける部分もありますし、何よりお子さんの成長がわかるような書き方がいいのでは」というようにおっしゃっていました。見守る保育という奥深いところも大事ですが何か基本に戻って大事にしたいことを振り返らせてもらった気がします。
そんな廣田先生から、「子どもの成長は神秘」であるともあり、ハッとさせられるような思いでした。
そんな廣田先生に西村氏からお言葉がありました。来年4歳児クラスをもつ廣田氏は少し不安げな表情を浮かべる中、いろいろ考えすぎてしまいがちな時に「今は目の前のことを一生懸命やれば自ずと結果がついてくる」ということでした。
大きなビジョンを描くことよりも今を一生懸命やっているからこそ、そこから経験をし、その経験で自分が形作られていくんだよというようなお言葉だったのではないでしょうか。
この言葉な森口氏も廣田氏に言っていたそうです。偉大な先輩たちの言葉には重みがあります。
ちょっと楽しく食べていてこれくらいしか覚えておらず申し訳ありません。

おすすめです!
なかなか内容が薄いですが最後までお付き合いありがとうございました。
報告者 本多悠里