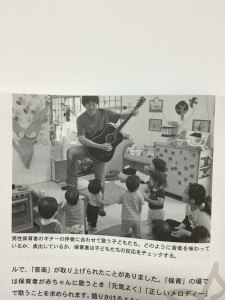先週の臥竜塾の報告で動物占いを考案された弦本將裕さんが書かれた絵本を紹介しました。
弦本先生とは過去にも何度かお会いしたことがあり、久しぶりにお会いできて嬉しかったです。
と言うのも塾長と対談をされたり、動物占いのセミナーに塾長が呼ばれたりと何度か弦本先生とコラボされていたので、
私もお会いする機会がありました。また私の父が個人的にも繋がりがあったので、そっちでもお会いする機会がありました。
父からというのは、動物占いを深く学び、試験に合格すると認定講師、認定カウンセラーの資格を取得でき、
動物占いの講師やカウンセラーとして活動が出来るのです。父が急にその資格を取得したのです(笑)
話を聞くと塾長がまだせいがの森保育園で園長先生をされているときに弦本さんが園内研修で訪れたというのを聞いて、
塾長が動物占いに関心があると知って、資格を取ったそうです・・・。
その影響から私も改めて動物占いの本をじっくり読み、少し学んでみました。
正直言うと「ただの占いでしょ?」と思っていましたが、本を読むにつれて、
いくつか今までの考え方が180度変わった言葉がありました。
それをいくつか紹介したいと思います。
「本当の自分」
自分のことは自分がよく知っていると思います。もちろん全てではありませんが、少なくとも他人よりは知っているはずです。
本には、自分を深く知ることで「自分と他人」の違いを理解するところに到達すると書いてありました。
まずは自分のことを知るために動物占いをしてみました。
100%ではありませんが、自分の性格など合っていましたが、それよりも新しい自分が見えたことです。
なぜ、自分はこういう時に、こんな行動をとるのか?こんな考え方をするのか?という事を見事に解説してあったのです。
それを読んでとても納得し、自分の短所も認められるようになりました。
人は誰でも苦手な人がいると思います。おそらく、それには何らかの理由があると思うのですが、
その多くは価値観や考え方の違いだと思います。
職場の人とトラブルがあった場合、二言目には「あの人とは合わない!」と言っているかもしれません。
少し話が逸れますが、自分の性格、趣味、考え方が一緒の人と出会うことは、ほぼないそうです。
そう考えると、しょうがないですよね(笑)
ましてや一度、自分とぶつかった人を受け入れるのは容易ではないと思います。
しかし、「自分とあの人では個性が違うのだ」という視点で見ることで、
相手の言動が検証として受け止められるようになるのです。
塾長が掲げた見守る保育10か条の6条に書かれある
「子どもは、職員の多様なチームによって、多様な社会との関わりを学習すること」
そして私たちが作ったポスターに書いた言葉は
「無理はしなくていいそれぞれの得意分野を活かす」
です。職員も子どもと同じように特性、個性があります。
それを、まずは十分に理解し、この人は何が得意なのか?何が苦手なのか?
苦手なことを無理にさせたことで、いい結果は出ません。それならば得意なことをさせた方が、周りにもいい影響を与えますし、なによりも本人が嬉しいはずです。
少し人間関係で困ったときは息抜きだと思って、やってみてはいかがでしょうか?
諦めがつくかもしれません。
つぎは「アキラメル」ことについて本に書かれてあったことを紹介しようと思います。(報告者 山下祐)