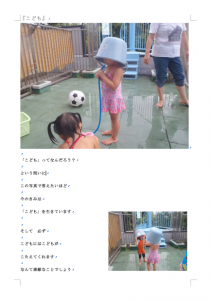子ども時代を“大人になるための準備”と考えた時、「発達の幅」が重要になると、前回報告させていただきました。社会というものを視野に入れると、その発達の幅は、同時に「多様性」をもたらしていると感じます。子どもたちは、そんな多様な環境の中で、自分というものを知っていく気がします。塾長は「人間というものは、他者を通して自分を理解する」と言っています。つまり、周囲が多様であればあるほど、自分という存在がより明確になっていくのではと思っています。母子関係だけよりも、親戚・地域・社会などとの関わりによって、人は自分を理解していくということだと思います。ということで、今回は、「多様性」についての考察をしていきたいと思います。
まず、自分というものを理解していく上で、多様な他者という存在が自分にとってストレスなく関わり合っていくかというと、そうでもないと思います。多様性という刺激は、適度な葛藤やストレスも多く生み出しています。先日の臥竜塾年間講座の中のディスカッションでは、「5歳児が0歳児にお手伝い保育に入ると、すぐに戻ってきてしまう。赤ちゃんがどうして泣いているのかが理解できなかったり、意志がなかなか伝わらないことにストレスを感じている様子。」といった報告がありました。年齢に限ったことではなく、性別・国籍・思考・価値観・性格・発達といった異なりから、このような葛藤やストレスを感じるのです。
しかし、塾長は、この経験から「調節する力」が育まれていくと言っています。なかなかコミュニケーションがとれない相手との関わりから、相手が何をしたがっているのか、何を望んでいるのか、何を伝えようとしているのかを探り、それに対して自分が試行錯誤して、相手との関わりや距離を調節いく過程にこそ、生きていく上で最も大切だとされている「対人知性」が育まれていくのではないでしょうか。つまり、場合にもよりますが、葛藤やストレスは決して悪いものではないということです。もちろん、共感することは大切だと思うのですが、目先に広がっている子どものそういった姿に、「かわいそう」などと悲観的なイメージを持つことよりも、その先にある「恩恵」に関心を持つことも必要です。それらの究極が、昔からことわざとして残っている「可愛い子には旅をさせよ」であると感じています。
また、塾長のブログでもよく取り上げられる単語として、多様性という言葉を変えた「ダイバーシティ」があります。近年、企業がこの言葉を掲げることが多く、企業内の人材を誰一人として無駄にはしない、多様な人材の採用や定着だけでなく、その先にある「活用」に注目を向けているようです。つまり、個々人の異なりを認め、尊重し、その「違い」に価値をつけ、組織内のパフォーマンス向上を目的とするわけです。塾長は、それらを「共異体」と表現し、数十年も前から保育園という場で提案し続けてきました。(知れば知るほど、塾長の偉大さが増していきますね…。)そういった、個々人の特性を優先される多様的な環境によって、子どもたちは、これからの社会に必要な大人になるための準備をしていくのです。
(報告者 小松崎高司)