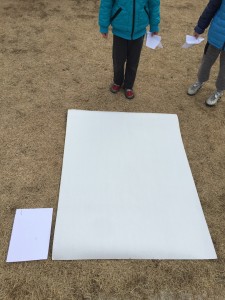先日、残り2か月の学童生活をどう過ごしていくかを子どもたちと話し合いました。
これは私ではなく、もう1人の学童職員がその機会を設けてくださいました。
このような話し合いに至った経緯は、全員で同じ時間を共有する際に、まとまりやメリハリがなく、子どもたちがどうしたいのかがわからないということからです。
学童での日常生活の中で全員が同じ時間を共有する時が2回あります。
1回はおやつの時間で、その際に今日の活動内容等を職員から子どもたちに伝えたり、その日開けるゾーンなどをお当番さんが皆の意見を聞き、決めていきます。
もう1回は、17時で一区切りとしていて、17時になる前に全員で1度集まり、お部屋全体を全員で掃除するというものと、17時以降のゾーン決めを行うものです。
この2回とも最近はまとまりやメリハリがなくなってしまい、時間までに終わらなくなってしまうことがしばしばという現状でした。
しかし、この2回に含まれるゾーン決めも17時前の掃除も子どもたちが決めたことなのです。
今回行われた話し合いの意図は、「子どもたちだけではまとまりもメリハリもなくなってしまって、せっかく遊べる時間も自分たちで潰してしまっているのが現状だから先生たちが一から十まで決めてあげようか、その方が遊べる時間が多くとれるよ?」と提案し、自分たちが普段どうしていくべきなのかを気付いてもらうというものです。
そこで各学年に分かれて話し合ってもらい、話し合いで出た案を紙に書いてもらいました。
書いてもらった内容に最も多く書かれていた言葉が「自由」です。
子どもたちが主体の学童、子どもたちの学童だからこそ月案からゾーン決めまでの全てを子どもたちが決めます。
子どもたちはそれを「自由」と捉えていたのでしょう。
あながち間違いでもありませんし、むしろ正しい捉え方なのかもしれません。
しかし、自由には責任が伴います。
話を聞いていると子どもたちはしっかりわかっているのです。
ただ、自分以外に多くの人が共に過ごしている学童では、全員で決めた事も「私が決めた事ではないから」と責任を逃れようとしてしまう子もいます。
これが今回の話し合いにまで至ってしまった問題の根底にあるものである気がします。
子どもたちみんなの学童であり、子どもたち一人一人に決定権があるということは、子どもたち全員で1つのチームであるということだと思っています。
よくチームスポーツで、チームの誰かが問題を起こしたら、連帯責任となり、チーム全員の問題となることがありますが、根本的には同じことが言えると思えます。
今回の話し合いでは、このようなチームの定義を感覚的ながらも子どもたちにわかってもらえていれば良いのですが…
今後の子どもたちの動向が楽しみです。
(投稿者 若林)