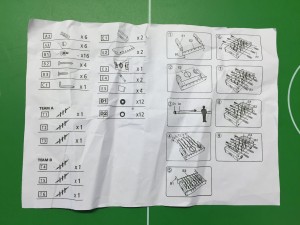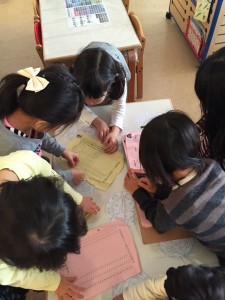園庭の運動遊具や園庭のあり方について、皆さんどう捉えるでしょうか。私の園でもそうなのですが、基本的に総合遊具は園庭の端にあり、真ん中は広い場所になっています。そこは三輪車で走ったり、ボール遊びをしたりと広い場所を使って遊ぶものをするときに使われることが多いです。一般的な保育園の園庭もそうであることが多いように思います。そのことについて、以前、ドイツの遊具メーカ-aibeのグリム氏と藤森先生の研修でグリム氏がこういったことを言われていました。
それは1.日本の園庭は遊具が少なく、様々な遊びができない。2.広いが一つの遊び道具しかない。ということでした。また、こんなことも言われていました。「日本人は遊具に信頼がない」つまり、「怪我するかもしれない」「落ちるかもしれない」といって、その遊具の本来の意図を理解よりも、怪我などのリスクを避けるということです。ドイツでは逆転の発想でした。

ロフトの下には木のチップが敷き詰められています。
たとえば、ブランコですが、「日本ではぶつかっては危ない」「落ちたら危険」といって公園から撤去されていますが、ドイツでは逆に「転落の経験も必要」という考えを持っていました。しかし、やはりぶつかると危ないので、座席部分はゴムにしているということでした。また、一番怪我をするのは降りるときであり、その問題は地面にある。だから、地面を柔らかい素材や木のチップを敷き詰めている。とのことでした。
「危険」だから取り除くという日本の捉え方と大きく違いますね。そして、その怪我や危険のためにバランスを養うことにより自分で怪我を回避するようにしているといっていました。このバランスということが何かと重要視されます。こういった目的のため、その遊具一つ一つに込められた意図をしっかりと繁栄されており、「経験」を通して、どう子どもたちを育てるかという意味合い自体が遊具メーカ-にも考えられていました。

フィーリングロードも一つのバランスを養う場所
こういった園庭の遊具の環境から前回の内容にもあった「運動」につながることが研修の中で触れられていました。というのも、前回のブログでもあったように日本は「運動」のとらえ方というと「走る」「跳ぶ」「投げる」といったように広いフィールドで力いっぱい走り回っている様子を運動と捉えることが多いです。そのため、園庭の環境もそういった活動ができるように意識されていることがとても多いです。

ドイツの園庭の環境
しかし、私が以前ドイツの保育園に見学に行ったときも、園庭の中に広い広場があることは少なかったように思います。園庭が日本のように走り回って体を動かすといったようなものではなく、多くの「経験」ができる場所としての意味合いが強かったように思います。日本の様に「園庭=運動」ではなく「園庭=自然環境や外でしかできない活動」といったイメージでしょうか。

乳児の環境でも不安定な場所が作られている。
そのため、岩が置いていたり、木などの自然環境があったりと日本の一般的な園庭とはまた違った環境でした。では、どこで運動をしているかというとそれは園庭だけではなく、室内でもしていることがありました。それもどちらかというとボール遊びだけではなく、アスレチックのようなもののほうが多かったように思います。それは前述にもあったように「バランス」が非常に重要視されているからなんでしょうね。
では、なぜ「バランス」が重要視されているのでしょうか。このときの話ではバランスを重視する内容が2つでていました。1つは「特別な機能を上げるのではなく、やりたいスポーツで発揮できるように 体のコントロール能力 と バランス感覚 を養うことが大切としていることです。最近ではスポーツの中でも「体幹」が重要と言われることが多いですが、バランス感覚はどのスポーツでも大切なことです。スポーツをするためにトレーニングするのではなく、自然と遊びの中でトレーニングすることでやりたいスポーツができるようになる。といったことですね。2つめは「集中力の強化」が言われていました。バランスを必要とすることは集中力を必要とします。難しければ難しいほどどう渡るかを考えます。そして、その経験が「問題解決能力」に繋がると考えられていました。
あくまでこれは遊具メーカーの考える遊具や園庭においてどう考えるかということの一端にすぎないことだと思います。しかし、この一つの話をとっても、私はあらためて考えることが多かったです。文部省のHPを見ても、日本人の身長は年々伸びているのに対し、運動量は低くなっています。「運動をできるようにする」のではなく、「運動を楽しくできる」ようにするにはどうしたらいいのか。そのために、どういったアプローチをしていくことが必要なのか。もっと幅の広い目線や意図で園庭においても環境を作る必要性をこの研修で感じました。
(投稿者 邨橋智樹)
私は東京生まれで東京育ちです。ですので正月など帰省することはありません。
ただ去年結婚をし、奥さんの実家に挨拶しに横浜に行くようになりました。
そこでは当然ながら奥さんのお父さんとお話をします。そこでよくお父さんから出る言葉があります。
それは
「ワイドに物事を見ろよ。」です。
某大手企業の営業マンを長い間続けられ、様々なところに出張に行ったそうです。
どこか地方の話になると
「知ってる、そこは何々が有名でいい所だね」と気さくにお話をしてくれます。
出張の際は1日早く出張先に行き、その土地を簡単ではありますが回るそうです。その土地をその目で見て肌で感じることでその取り引き先の土地を理解し、会話が弾むそうです。
そこで感じるのはやはり、
「百聞は一見に如かず」という言葉が思い浮かびました。
更に私の中で繋がってくるのが、塾長です。塾長は私たちを様々なところに連れて行ってくれます。それはブラヘイジであったり、ふと買い物に行った際に立ち寄ったりする場所であったりと様々です。
様々な場所に行き、自分の目で見る機会を与えてくれます。
ブラヘイジでは
「ただ歩いているだけでは意味がないよ。なにか保育に繋がることがあるかもしれないから意識して見るといいよ」という言葉も頂きました。
お陰様で歩くことが好きになっています。つい最近は奥さんと東京駅から表参道まで歩くなど楽しめています。
塾長の言葉もワイドに物事を見ることで発見できることだと思います。
改めて奥さんのお父さんと話すことで思い出すことがあり、日々どんな所に行っても感じることは様々ですがなにかヒントがあるかもしれないと心掛けることを更に意識したいと感じます。
営業マンの仕事と保育に少し通じるものがあるのかもと少し感じる出来事でした。
そして正月休みから背筋がピシッと伸びるようなお話ができました。
当たり前のことを書いてしまいましたが、私はすぐに初心を忘れがちになります。このお正月で様々なことを考えましたので、新年しっかりと地に足をついて楽しんでいきたいと思います。
なんだか抱負のようになってしまいました…
(報告者 本多悠里)
以前、塾長のブログで「ケ」と「ハレ」が取り上げられたことがありました。日常の生活を「ケ」、特別なことがある日を「ハレ」。毎日が「ケ」の生活は、メリハリがなくなり、生活リズムが取りにくくなります。なので「ケ」の中に「ハレ」の要素をうまく取り入れて、人間は生きてきたそうです。
そして指針にもありますが、生活リズムが安定することは、子どもにとって情緒の安定につながります。
「ケ」と「ハレ」の詳しくについては、その時のブログを読んでいただきたいのですが、そんな「ケ」と「ハレ」は現在においてはバランスが崩れてきているといわれます。
例えば、お正月では、おせちを食べる家庭が少なくなっていることや、お餅を年中食べるようになり特別なことではなくなるなど、「ハレ」としての存在が薄れてきているといわれています。
私もついこの間まで実家に帰っていたのですが、幸いなことにおせち料理もあり、まだ「ハレ」としての特別な感じを感じました。ですが私がおせち料理よりももっと特別な感じを感じたことがあります。
それは「たくさんの人と会う」ということです。
普段、私は娘1人に夫婦と3人で暮らしています。とても楽しい生活ではあるのですが、いつも考えるのが、もしおじいちゃんおばあちゃんが近くに住んでいたらどうなるのだろうということです。
私の実家は、遠く、なかなかおじいちゃん、おばあちゃんなどに会うことができません。
ですので、たまに帰省して会える時は、娘も大興奮で、先日帰った時も、もうこれ以上ないというくらい遊んでもらい、またいろんな経験をしました。
そして、帰省するたびに感じるのが、そこでの刺激から、新しい言葉を覚えたり、今までできなかったことができるようになったりという娘の成長です。
現代においては行事としての「ハレ」は薄れてきてはいると思うのですが、核家族という形態が増えてきている中、なかなか会えない人と会えるという意味での特別感は強くなってきている気がします。
自分が子どもを持つことで、お正月といった行事や、夏休みなど長い休みが、子ども達にとって大きな意味を持つことに気付けたのですが、今度はそれが園にいる子ども達すべてにそんな関係があると思うと、子どもたちのお休みもとても特別なことに感じてしまうのは私だけでしょうか。お正月明けの保育が今から楽しみになってしまいました。
(報告者 西田 泰幸)
そろそろ私の保育園でも発表会があります。それぞれのクラス、特に幼児のクラスは練習をすることも多くなってきました。前回のブログでもあったように実に予行を見ていても、それぞれのクラスの色が出ていますし、それぞれのクラスの課題や良い点などもたくさん見えてきました。
そんな中、発表会の様子であることに気づきました。それは舞台の上や出番を待っているときにもかかわらず座り込んでしまう子どもたちが多いのがとても気になりました。そこでその子どもたちにインタビューをすると、面白い共通点が出てきました。ある子どもは「立つと足が痛くなる」、そして別の子は「立つのがしんどい」。そうです。子どもたちは「立つ」のがしんどかったのです。確かに考えてみると座り込んでしまう子どもたちはフラフラして立ち歩いているか、座り込んで膝で滑って遊んでいます。普段の遊びを見ていても、部屋遊びでは寝転がったり、座り込んでいる様子が多いです。立っているのがしんどい様子が普段の様子からも見て取れました。
なぜ、そうなるのか、職員の先生がたと話していると、つい、立っているとけんかが起こるので日頃から座らせて話しをすることが多いといっています。
たしかに、こういったことは日常でよくあることです。もちろん、取り組みが楽しければ座り込むこともないのでしょうが、ある男の子は「劇は面白いんだけど、しんどくなっちゃう。」という子もいました。
私の今いる地域の大阪は電車がある程度充実していてもまだまだ車中心の土地で、歩いてどこかにいくというよりも、すぐ車に乗って移動することがとても多いです。また、「立つのがしんどい」という子どもほど、やはり散歩に行っても「しんどい」という子どもたちでした。「聞く」ということに体力も、もしかしたら因果関係があるのかもしれません。
今、園に来ている体育の先生に子どもたちの「体力」に変化はありますかと聞いたところ「確かに最近の子どもたちから(疲れた・しんどい)という言葉を聞くことが多くなってきていますね。今まではそれほどなかったのですが・・・」というような言葉をもらいました。
調べていくと、当然今の子どもたちの体力は昔に比べれば、どんどん低下していると聞きます。では、今の子どもたちはどのように体力に変化が出ているのかを調べるために文部省のHPを見ていると、どうやら子どもたちの体力の低下が見えてきたのは昭和60年頃かららしいのです。また、その調べ方は昭和39年から始まった「スポーツテスト」です。日本では昭和36年に戦後の復興と東京オリンピック招致が決定したことにより、スポーツの関心の高まりからできた「スポーツ振興法」ができました。そして、その流れの中に運動能力テスト、体力診断テストからなる「スポーツテスト」が始まったのです。その中で、スポーツテストの項目は何度が改訂されているそうです。また、このスポーツ振興法の中で「スポーツ振興基本計画」というものがあり、生涯スポーツ、競技スポーツの振興と共に、これらと連携しての学校体育・スポーツの振興が施策の三本柱として盛り込まれています。その中で「児童生徒の運動に親しむ資質・能力や体力を培う学校体育の充実」が掲げられ、その到達目標に「たくましく生きるための体力の向上を目指し、児童生徒の体力の低下傾向を上昇傾向に転じるために、児童生徒が進んで運動できるようにする」と明記されています。
「たくましく生きる」というのが一つのキーワードであるように思います。また、「児童生徒の運動に親しむ」というのも今の日本の様子ですね。しかし、そもそも「運動」とはなにをもって「運動」というのでしょうか。日本の「運動」のとらえ方というとやはり「走る」「跳ぶ」「投げる」といったように広いフィールドで力いっぱい走り回っている様子を運動と捉えることが多いように思います。実際、私の保育園でも園庭にでて、鬼ごっこやボール遊びをしています。しかし、以前、ドイツの遊具メーカー Aibeの方の研修を受けたときにまた、違う視点で運動機能や運動遊びを捉えていました。そのときのAibeの方と藤森先生の話を基にもう少しこの「運動」という部分を掘り下げてみたいと思います
(投稿者 邨橋智樹)
そろそろ今年も終わりに近づいてきました。そうなると忘年会など飲み会が多くなるシーズンですね。私も先日から実家に帰省しました。
そして、偶然にも小学校の時の同窓会が帰省の日の夜にあると連絡があり、また当時の担任の先生も来られると聞き、卒業してから一度もちゃんとお会いして話した事がないので、是非会って当時の思出話をしたいと思い参加しました。もちろん息子が寝てから参加したので、遅れての参加です。
会場は同級生が親が経営している中華料理店で一緒に働いているので、そこで行いました。
お店に入ると、まず驚いたのは人数です。私はてっきり大勢いるかと思いきや、私を含めてたった6人でした(笑)
ただ、その方がゆっくりと思い出話に花を咲かせるので、個人的には良かったです。
さて、もちろん小学校の思い出話になるのですが、やはり皆から私の印象は良くも悪くも色々な意味を含めて強かったそうです。ただ先生からすると、そんな自分でも泣き虫なところが良かったと言ってくれました(笑)まぁ今もそんな感じですね。結局は大人になってもベースは変わらないというのが結論です。
ただ小学校の頃は確かに楽しかった印象が強いですが、だからといって鮮明に覚えているか?と言うと意外とそうではなく、かえって嫌な思い出の方が残っています。先生に怒られた時、友達とケンカをした時などです。
数年前に同じように帰省の際に母が私の幼稚園の頃の連絡帳を出してきました。
それを読むと、まぁひどいこと(笑)今で言うと確実に加配が必要な子どもですね。気に入らないとすぐに手を出すし、物は壊すし…。その中で一番ショックな内容が書かれていました。
それは幼稚園~小学校まで仲が良かった友達がいました。親同士も知っていたので時には夕飯もご馳走になったりと、よく遊んでいました。しかし、その日の連絡帳にはその友人の事が書かれてあり
「◯◯君がたすくちゃんにいじめられるから…と言って幼稚園に行きたがらないそうです」と。
それを読んだ私はとてもショックを受けました。仲がよいと思っていたのは自分だけで、実は彼をいじめていたんだ…と。
よく塾長の講演で
「子ども同士のトラブルでひっかき、噛みつきで怪我をしてしまったら、危害を加えた方よりも、された方をしっかりケアをしなさい。やった方はすぐに忘れるけど、やられた方はショックが大きい…」
また塾長が小学校の教師をしていた時に、悪の中学生を家に読んで勉強を教えていたりと世話をしていた時の話でも、だいたい非行に走ってしまう少年は過去にいじられていた少年が、自分を守るためにやる側に回ったり、非行に走ると…。
これらの話しを講演でも何度も聞いていたので、自分の連絡帳を読んでいて、すぐに頭の中に塾長の話を思い出しました。
子ども同士のトラブルが起きたときに、つい悪い方を強く怒ってしまいます。もちろん悪いことを本人にちゃんと伝えることも大切ですが、それよりもショックが大きく、心に傷を負った方のケアをしっかりしないといけませんね。(投稿者 山下祐)
最近の科学離れに対してドイツでは「小さな科学者」という取り組みが行われているそうです。
それは、科学的実験の例がファイルとして作成されているなど、科学が身近なものとして感じられるようにされてるそうです。
学童でもそんな「小さな科学者」を思わせる出来事がありました。
もう年末ということもあり、子ども達と大掃除を企画して、家具をすべて動かして掃除をしたのですが、子どもたちのハングリーな企画力の年内最終日に、近くの子ども広場との一日コラボイベントというものがあり、また少し部屋は汚れ気味に、、、。
それどころかそのイベントの片付けだけで、夕方になってしまい残っている子も4人ほどになりました。
来年へ掃除は持ち越しかなと思っていたのですが、そんな中、ポロンと出てきたのがメラミンスポンジ。
そうかこれだと思い、残っている子どもたちに、「ちょっと遊ばない?」と声をかけました。
なかなか大きなイベントの後だっただけに、初めはのりが悪かった子どもたちでしたが、机に残る鉛筆や色鉛筆の後を「こするとどうなるでしょう?」みてと、メラミンスポンジとぞうきんを渡すと、、。
中にはどうなるか知っている子もいましたが、普段使っている机が、とてもきれいになっていく様子に子ども達は興味津々。
「次はこっち」、「○○くんはこれお願い。」「まだお迎え来ないよね?」と子ども達で相談しながらとても集中して楽しんでいる様子でした。
身近なものから科学を楽しむ。そんなことを思い出させてくれる出来事でした。
来年また学童が始まり、きれいになった机を見せながらまた他の科学にも取り組んでみようと思います。
(報告者 西田)
今度の12月25日に学童でクリスマス会があります。
クリスマス会といっても、職員は何もしていません。
クリスマス会をやるという所から、その内容、日程まで子どもたちがすべて決めています。
学童では、毎月の予定を子ども達みんなで決めているのですが、クリスマス会はその日程を決めた後、そこからさらに計画が必要と考えたのか、クリスマス会係というものを決めていました。
そんなわけで、最近は登所してくると係の子どもたちが急いで宿題を終わらせてから、集まって「あーでもないこうでもない」と話をしています。もちろんその係は1年生から3年生まで様々でそれぞれの視点の考えを聞いているだけでも面白いのですが、そこであることに気付きました。
それは、クリスマス会の係が会用のおやつやジュースなど食材を買いに行くという時でした。買い物に行こうとしている係とは別に、残っている係がいたので、買物に行く係に「みんなでいかなくていいの?」と聞くと、「あっちはいいの」と返されました。
「ああ、ちゃんと分担しているんだな」と思い、私はそのまま残っている職員だったので、残っている係の子に、「今買い物の子達は行ったよ~」というと、「えっ、そうなの」と知らない様子でした。
「あれ、変だな」っと思い、詳しく聞いてみると、初めに係を決めた時に、企画の係、料理の係、ポスターの係というように分担をして、後はそれぞれの係がしっかりやるということで動いているらしいのです。
まるで、大人と同じくらいの連携を見せ、そして何よりもそれぞれがしっかりとできるから大丈夫という信頼関係に少し感動してしまいました。
これからそのクリスマス会が行われる日が来るのですが、どんな内容になるか、今から楽しみでしょうがありません。
(報告者 西田泰幸)