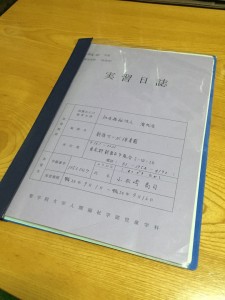先日、学童クラブにいた時に驚かされる出来事がありました。
学童クラブでは学校から帰ってきてから、宿題をやったり、遊んだりしながら降所予定の時間になったら自宅へ帰ります。降所は、明るいうちは一人で家まで帰る子が多いのですが、外が暗くなる時間帯はお迎えのみの降所となっています。
また、習い事をやっている子もいて、一時的に学童クラブから出て、また学童クラブに帰ってくることもできます。
最近少し困っているのが、この習い事がなかなか終わらず、学童クラブに戻ってくるのが遅くなると、一人で帰る予定だった子が、暗くなってしまい帰れない時間になってしまうことがあります。
この間も、習い事に行った子が教えてもらうことが多かったのか戻ってくるのが遅くなり、学童に来た時には外が暗くなり始めていました。まだ、一人で帰っても大丈夫な時間ではあったのですが、その子は「暗くなり始めているから、一人で帰るのは怖い」と帰れませんでした。保護者に連絡を取り、お迎えに来れるかを確認したのですが、連絡がつかず、学童でしばらく待つことになりました。
そんないつもと違う様子に、他の子をお迎えに来た保護者が、「どうしたんですか?」と事情を聞いてくれました。そして、「良かったらお家を知っているので、一緒に送っていきましょうか?」と声をかけてくれました。
その子の保護者と連絡が取れていなかったので、とりあえず連絡が取れてからとお話ししたのですが、その後、また他の子を迎えに来た保護者も「どうしたんですか?」「よかったら送っていきましょうか?」。また別の保護者も「送っていきましょうか」と声をかけてくれました。私の記憶する限り、声をかけてくれたどの保護者の家も、それほどその子のうちから近くはないのですが、保護者同士のつながりの深さに驚かされました。
そこで感じたのが、実は「帰るのが遅くなっている子」も、「声をかけてくれた保護者」も、保育園から学童に上がってきた家庭で、保育園と家庭がいい関係を築くことができれば、自然と保護者同士もよい関係になるのではと感じました。
良い保育をすることそれは周りにも影響がでるものなのですね。
(報告者 西田)