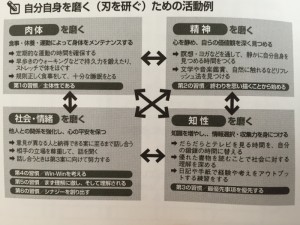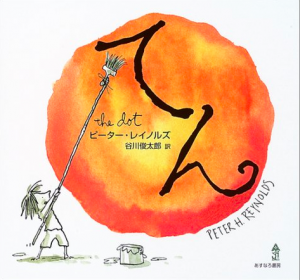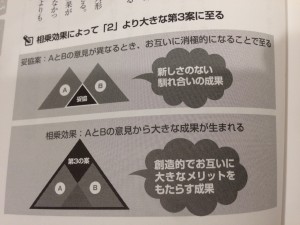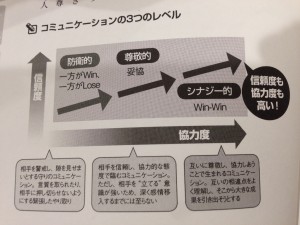先週の日曜日に新宿区学童保育連絡協議会が主催の運動会(略して連協運動会)がありました。
新宿せいが学童も毎年参加し今年で8回目の参加になり、そして悲しい事に最後の参加です・・・。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、来年度から隣の小学校に学童が出来る代わりに、
今年でせいがの学童が廃止になることになりました。
そして学童の部屋が空き部屋になる分、保育園の定員も増加になります。
ですので、来年度から新たな新宿せいが保育園が誕生します。
今回は最後という事もあり、特別な思いを持って臥竜塾全員で運動会に参加させていただきました。
もちろん塾長も来てくださいました。
まず連協運動会の簡単な説明をします。
新宿せいが学童を含め、連協に加盟している学童、児童館が紅白の2チームに分かれます。
そして「大玉おくり」「玉入れ」「リレー」「綱引き」などを行い点数で勝敗を決めるという、
至ってオーソドックスな運動会です。
中でも一番最後に「館対抗リレー」という競技は、紅白関係なく、
純粋に施設ごとの勝負なので、ある意味、総合優勝よりも価値が高かったりします(笑)
ちなみに新宿せいがは2年前に優勝。去年は3位と悔しい思いをし、
今年こそはリベンジに燃えての参戦です。
ちなみに「館対抗リレー」というのは小学校1年、2年、3年・・・大人と順番にバトンを渡す縦割りリレーです。
新宿せいがは男性が多く、そして若く、そして運動ができると三拍子揃っているので、
他の施設に比べると明らかに大人の平均年齢が若いので、
去年から、職員は男女一人づつと規制がかかってしまいました(笑)
そんな規制がかかっても新宿せいがは今年も順当に決勝に進みました。
そして、決勝がスタート!!
せいがの第一走者の小学生は卒園児で、保育園の頃から運動神経抜群の男の子です。
当時は多動気味な部分もありますが、運動になるとピカイチです!
もちろんスタートと同時に1位になり2位と大きな差をつけてバトンを渡しました。
そのあとも2位に差を詰められては離しの繰り返しで、なんとか1位のままアンカーにバトンを繋ぎ・・・
アンカーは元ラグビー部の筋肉ガチガチの体育会系の保護者(もちろんお父さん)です。
この日のために体を作ってきました!と言わんばかりの体つきでした。
そんなお父さんが抜かれる理由もなく!そのままゴールテープにトライ!!優勝を果たしました!!
最後の運動会で有終の美を飾ることができ、本当に感動しました・・・。
さて、感動話しはここまでにしておきましょう。
塾長が月曜日の朝会でこんな話をされました。
「年々、連協運動会に参加する保護者、子ども達が減ってきているそうです。また小学校、中学校でも父母会の存在も要らないのでは?という声もどんどん出てきて、
うちに父母会があるという事に、驚く人もいるそうです。それだけ横のつながりが減ってきているという事になります。
それに比べて、うちの学童は子どもも保護者の参加者も他の学童や児童館の中でも一番多かったです」
と・・・。
確かに1年目の運動会に参加した時はせいが学童が一番少なかったのを覚えています。
それに比べて他の施設は子ども、親の参加者も多く、少し寂しかったのを覚えています。
それが年を重ねるうちに、参加者も増え、いつしか他の施設と同じくらいになり、
最終的に一番多くなりました。
今年の館対抗リレーはせいが学童だけで4チーム出場しました。
個人的に嬉しいのは現在、学童に通っている児童はもちろん、
過去に学童に通っていて卒所したOBの小学生も多く参加している事になんだか嬉しかったです。
中には小学5年生で私と同じくらいの身長の男の子もいて、
それはなんだかショックでした・・・(笑)
また学童の保護者から、こんな話しを聞きました。
他の学童は人数が減ってきているのにせいが学童は減るどころか応募も増えてきていると。
おそらく新宿せいが保育園の周囲から図書館、児童館が閉館になり、放課後に子どもが過ごせる場所が少なくなってきているのも影響はありますが、
塾長は学童に行く子どもが減ってきている事に対して「危険」と言っています。
それは学童に行かないということは、家の中で一人か数人でゲームをしている方が楽しく、
外に出て色々な経験もしないということです。
塾生の若林が学童での活動を色々と報告していますが、
月案会議を自分たちで行い、活動の内容、ルールなど話し合って決めています。
学校ではなかなか経験できない活動を学童ではできる。
これは小学生にとっては貴重な場所だと私は思います。
そんな貴重な場所が来年度から無くなるのは・・・寂しいですね。
今回、最後の連協運動会に参加し素敵な思い出が作れた反面、
都内の小学生の子ども達を取り巻く環境の実体を直に触れる機会になり、
色々と考えた一日となりました。
最後に・・・
運動会は中学校の校庭を借りて行うのですが、トラックが本当に小さく、おそらく50m~80mかと・・・。
トップスピードでコーナーを曲がると本当に転倒するくらい小さなトラックで、過去何人もそのコーナーに犠牲になりました。
今年も一人職員で犠牲になり、しかも2年連続で・・・私よりも「若」いのに・・・。
運動不足は恐いですね・・・。
またいきなり走るのは危険なので、ウォーミングアップを学校の外で行った際に、転倒し流血した職員もいました。
塾長は言います。
「運動不足の人が急に動こうとすると、頭では以前のように動こうと指令を出しても、体が追いついてこなくて、足が前に出てこないんだよね・・・
だから雑巾がけは有効だよね」と。(投稿者 山下祐)