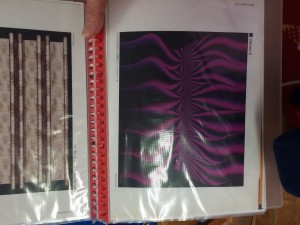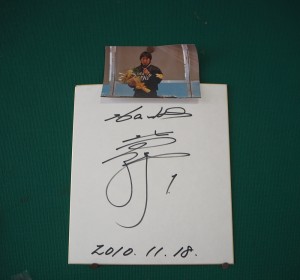獣が何度も通っている間に道が出来る「獣道」があるように、子どもが通っている間に道ができる「子ども道」というのもあると思います。先日、その「子ども道」を散歩先で見つけることが出来ました。その公園は、「第二の園庭」とも言われているくらい、子どもたちと頻繁に訪れる場所でもあります。
私も幼い頃、雑木林の中の道無き道を進んで、小さな小空間を見つけ、感動し、そこを「秘密基地」にして遊んでいた事を思い出しました。そうして出来た“道”には、自分の歴史があり、想いが潜んでいるのだと思います。目の前の子どもたちにも、きっと“この先に何があるか”を求めたり、そこまでに至るまでの道のりがあったのだと思います。そう考えていると、ずっとこのファインダーを覗いていたいといった感情が沸き上がってきました。
私はこれまで、「道」というのは、人や物が通るべきところといった解釈をしていました。既に道は存在していて、ある目的を達成するために通る手段や方法であると思っていました。よく、ある目標があって最短でその場所に行くための方法として、「その道を通った人に聞く事」があげられます。実際に経験した人の言葉というものは、やはり心に響く説得力とノウハウを感じるとることができますものね。
しかし、子どもたちの姿を見ていると、私が思い描いていた「道」とは異なる「道」を歩んでいる事が多いと感じるのです。最初に話した、「獣道」のような「子ども道」のように、誰も歩んだことがない道を歩もうとする傾向があると感じています。一見、その行為というのは遠回りのようにも感じますが、様々な経験と瞬時に判断して動く対応力などを身につけるという“遠回り”が、子どもならではの「道」なのかもしれないと思いました。
つまり、私たちと子どもとの間には、「この道を通ってくれば安心だ」「この道に間違いはない」といった大人の意見と、「そんな道はつまらない」「こっちの方がワクワクする」といった子どもの意見との相違が存在してしまうということだと思います。その相違が、子どもをがんじがらめにさせている原因でもあり、“ケガ”というリスクマネジメントととの折り合いである気がします。
道無き道を進む子どもたちを、いかにして見守るか。挑戦して発達を遂げようとしている子どもたちをいかにして見守るか。そのテーマは、子どもと大人との永遠のテーマでもあるのだと思います。私たちは、何かに駆り立てられながら進む子どもたちの「子ども道」を後から追いながら、その道の途中にある子どもの心や体の動きの形跡に、敏感に反応しなくてはいけないのだなと、ふと、そんなことを感じました。
(報告者 小松崎高司)