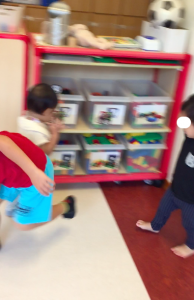体勢を立て直し、再挑戦する1歳児クラス男の子の玩具箱の中に、

残りのブロックを入れる5歳児クラスの男の子。

玩具を入れに戻った1歳児クラスの女の子は、

ここで自らお集まりへ向かう体勢に。

5歳児クラスの女の子のお役目はここで終了となります。
本当にお疲れ様でした。

1歳児クラス男の子は玩具箱を棚に戻すという最後の仕事に苦戦中。
ここからがとても素敵と感じた部分なのですが、

集めてきた残りのブロックを入れ、

すっと手を差し伸べます。
そして、

無事収納。

その子が納得できているかを確認するかのように表情を伺うかのような5歳児クラス男の子の視線。
男の子は納得していた様子で、

飛び跳ねて喜びます。
その姿に、

ちらりと視線を送る彼。
なんともクールですね。

ここで彼のお役目も終了します。
しかしまだ、給食の場へその子が向かっていませんね。

そんな中、残っていたブロックを発見。
それを、まるでフォローするかのように、

5歳児クラス、もう一人の男の子の登場です。

玩具棚まで付き添い。

男の子のブロックと自分のもっていたブロックを入れて、
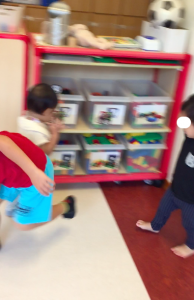
一足先に

給食の場へ。

その後を追うように給食へ向かう1歳児クラスの男の子でした。
13年目に入られました塾長藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2017年10月3日『社会を構成する他者』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)
「森口は、発達の最近接領域を考える上で、二つの重要なポイントがあると言います。一つは、同じ文化内に所属する、自分よりも能力のある構成員こそが子どもの発達を支援することができるという点です。これが、私の考える「異年齢保育」を行なう一つの理由です。異年齢の子どもの存在こそが、「同じ文化内に所属する、自分よりも能力のある構成員」であると考えるのです。もちろん、同じ年齢からの支援も発達には影響をしますが、より刺激が大きいのが異年齢からの刺激だと思うのです。もちろん、子どもと同等の能力を持つ他者(友だち)は、模倣などを通じた相互学習や共同学習によって、子どもが自分ではできないことをできるように導くことも示唆されています。
もうひとつの重要なポイントは、子どもの発達を知るには、現在の発達レベルは現在の発達レベルであり、潜在的な発達レベルを知ることができるような指標が必要だと訴えた点です。
このように、ヴィゴツキーの考えでは、他者が子どもの発達に重要な影響を与えるということです。」
1歳児クラスの男の子が玩具箱を片付け、給食へと向かう約1分の間にこれだけの関わりがあったことに驚くのと同時に、大人の介入なく目的へと向かっていく様子はまさに子ども社会の存在を強く感じさせるものでした。
異年齢の積極的な関わりを生み出すお手伝い保育。これからもその中で生まれるドラマを追っていこうと思います。
(報告者 加藤恭平)