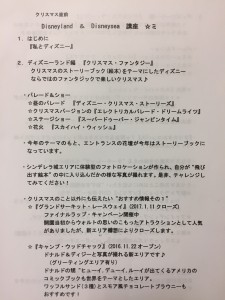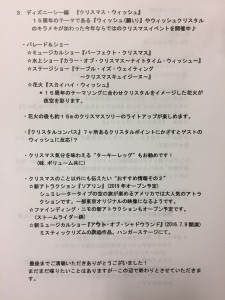「私はよく講演でこのように言います。〝私の声は眠くなります。職員会議では職員がよく寝ています(笑)〟」
お寿司を食べ、お腹がいっぱいになり、暖かな部屋で始まったこの日の園内研修最後のプログラム〝藤森先生による講演〟。

笑い声が部屋に起きます。いつもの職員会議の時のような和やかな雰囲気で講演はスタートされました。

テーマは〝乳幼児保育〟です。
特に最近の講演内容の中心とされている乳児保育についてお話は展開されていきました。
12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2012年3月13日『産後』の中にこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)
〝集団における子育てと母親だけに依存しない子育てのおかげで、離乳を1年未満に終え、次の子を産む準備に取り掛かれるのです。母親一人で子育てをするチンパンジーは、離乳は4歳なのです。しかし、チンパンジーは生きているあいだはずっと出産をします。それに対して、人間は出産期は短いために、集団での子育てをすることによって離乳を早め、それが人間を多産にしたといわれています。〟
オランウータンは7歳まで、ゴリラに至っては3歳と比較的短いのですが、それはオスが子育てに参加をするからだそうです。ゴリラの背中が白くなって声が低くなるのは、赤ちゃんの気をひく為という説もあるということですから面白いですね。
〝人類は、オランウータンのように離乳を遅くさせ、出産を待っていたら、一生のうち、2人も産めない計算になってしまいます。それでは繁栄していけないので、人類は毎年子どもが生まれるように5ヶ月で離乳を開始し始めます。その為に人類はまず家族を始めとする〝族〟という単位の集団をつくり、やがて村中で面倒をみるようにしました。〟
このことは『臥竜塾』ブログ2013年8月23日『出産2』の中でもこのように紹介されています。
〝出産について私がよく講演で話すのですが、人類は直立で立つことによって大きな脳を獲得することができた半面、産道が狭く、楕円形になったために出産に人の手を借りなくてはならなくなったということから、人類は一人では生きていくことができない宿命を背負ったと思っています。〟
写真後ろのグラフをご覧いただいたことのある方はおわかりになられると思うのですが、脳のEQ(Emotional Controlの略、感情をコントロールする力)が育つ時期、赤ちゃんにとっては脳が大きくなるこの時期、が大体、次の子が生まれてくる時期にあたります。だから我慢を覚えることができ、そしてここで感情をコントロールする力、我慢する力が育まれなくてはこのあとはとても無理であるということを藤森先生は強調されていました。
1歳〜1歳半でそれはピークに達します。乳児保育の大切さはここにあり、つまり〝0歳児クラスの保育〟が重要であり、脳を大きくして、受け入れ体制を広げてあげることが重要であると言えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このような形で、藤森先生のブログを引用しつつ、先生の講演を聞きながらとったメモを元に、その内容を咀嚼した上で報告をあげていこうと思いながら、書くことに至るまでにとても時間がかかってしまいました。「100ページ以上のスライドの中からほんの15ページ」程の内容と藤森先生は仰っていましたが、時間にして2時間、本当に心打たれる内容で、生臥竜塾ブログを読んで下さっている皆様に少しでもその内容が伝わればと思い、最後まで書き上げていきたいと思います。
今年も一年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(報告者 加藤恭平)
先日、年内最後の園内研修が行われました。
今回のプログラムはこちらです。
1.クリスマス直前!ディズニーランド&シー講座
2.藤森先生による講演
研修が始まる前に個人的にとても感動したことがありました。4F会議室で行おうと企画していましたが、来客の方がお見えになられ、セッティングすることも出来ないままに開始時間は迫っている、といった状況になりました。
すると、「3Fはどうですか?」と、ある先生からアドバイスをいただきました。
その機転にも個人的にとても驚いたのですが、それからの準備の早いこと!その手際の良さに二重の感動を覚えました。

そして、あっという間にセッティングが完了し、園内研修がスタート!
当初予定していた時間と変わらないスタートが切れたのも、また、いつも予定通りに始めらるのも、サポートしてくれる先生方のお陰であることに改めて気付く思いがしました。いつも本当にありがとうございます。
プログラム1.〝クリスマス直前!ディズニーランド&シー講座〟

第1章〝私とディズニー〟から始まる、ディズニーにとっても詳しい先生によるお話を聞きながら、皆でお寿司を囲みました。
その先生から許可をいただき、その際に使用したレジュメを公開します!
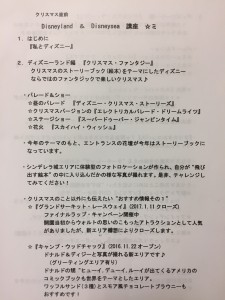
レジュメ1
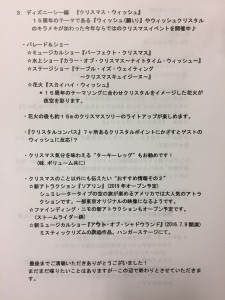
レジュメ2
前日打ち合わせではあまりにも膨大な情報量に圧倒されてしまいました(笑)その中からピックアップされた選りすぐりのクリスマス情報となっています。ご一読下さい♪
ディズニーランドの開園日と藤森先生のお誕生日が同日4月15日であることにいつも勝手に縁を感じてしまいます。子ども達を、そして子ども達を想う大人への想い。それは、新宿せいが保育園もディズニーも共通のものかもわからないと思った、この度の講座でした。
さて、その間に、臥竜塾生柿崎先生、西村先生が4Fをセッティングして下さいました。この間の準備の早さにも、本当に感動してしまいます。余裕でお寿司を頬張るお二人。本当に感謝です。
この後は4Fで藤森先生のお話を聞きます。次回の報告で、詳しくお伝えしていきます。
(写真提供:金塚由衣先生 報告者:加藤恭平)
ほうきを手にした子ども達。この後どんな展開が待っているのでしょうか。

山下先生「とりあえず自由にやってみようか。」

なんとなく今までに見てきたすいすい組(5歳児クラス)の動きを見よう見まねでやってみているような感じに思えました。

ほうきの順番を待ちながら、その場を見守る子ども達。
早めにお迎えに来られた保護者の方の姿も見られますね。こういう形で日々の保育を見ていただけることも、とても大切なことだと思います。
山下先生「じゃちょっと交代してみよう。」

「はいどーぞ。」交代も思った以上にスムーズ!
何か特別な意識がらんらん組(4歳児クラス)の子ども達に芽生えつつあるようです。
ここで山下先生からの抜擢を受け、

ちりとりと小ぼうきの担当に。

熱心にやっていました。

食器を片付けることも忘れてその姿に見入るわいわい組(3歳児クラス)の子ども達(笑)
小さな伝承が、こんな場面の積み重ねの中にあるのかもしれません。

協力して、とても上手に集めていました。
12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2013年9月20日『育児の見直し』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)
〝日本では、乳児において特定な人をひとりの個人と読み替えて、いつも同じ人と接することが落ち着くとか、同じ年齢で過ごすことが落ち着くとか思っている保育関係者が多いのですが、それは、本当の意味で情緒が安定しているわけではなく、刺激をあまり与えないことで落ち着いているように思えるだけだと早く気がついてほしいと思います。ジャレド氏ら人類学者たちが、小規模社会を観察してみて、彼らが情緒的に安定しているのは、人と会話して過ごす時間が、私たちよりもはるかに多いということも理由の一つであるといいます。
私たちは、直接人と会話をするよりも、書籍などといった、外部から提供され、受け身で享受する形の娯楽で消費される時間が多いのです。さらに、ジャレド氏ら子育てについて、このように観察しています。「小規模社会では、は子どもたちが、幼いころから社会性を身につけていることは驚きに値する。彼らの性質や性格や人間性に感服し、自分の子どもにもそれを身につけさせたいものだと願う人は、現代社会にも多い。しかし、その実、われわれの言動がひいては子どもの成長発達の阻害につながっている。(中略)
育児は、学問で学ぶことではなく、経験からよいものが伝承され、残っていくものであると私は思っています。〟
「自由にやってみよう。」数少ない言葉がけでこれだけのことができるに至ったそのプロセスの中に、大人からのほうきやちりとりの使い方の指導があったかと言えば、なかったとは言えないでしょう。ただ、一つ言えるのは、日中の活動の中に例えば一斉活動のような時間を設け、子ども達に受け身となる体制を整えた上でほうき、ちりとりの指導をしたことは一度もありません。
わいわい組(3歳児クラス)の子ども達が手を止めてらんらん組(4歳児クラス)のやっていることに見入っているあの姿のように、きっとらんらん組(4歳児クラス)の子ども達もまた、すいすい組(5歳児クラス)の子ども達の姿を見て、自発的に学び取っていったものと思います。
〝育児は、学問で学ぶことではなく、経験からよいものが伝承され、残っていくものであると私は思っています。〟
本当にそうだと思いました。
さて箒を終えた子ども達。いよいよお待ちかねの、あの時間です!
(報告者 加藤恭平)
給食が終わると、おもむろにらんらん組(4歳児クラス)の子ども達が動き始めました。

山下先生「やりたい子だけでいいからね。」その都度声をかけられていましたが、全員参加の様子です。
「わいわい組(3歳児クラス)は早く上(午睡部屋)に行って!」とらんらん組(4歳児クラス)の女の子が言います。言葉の端々から気合い(?笑)が入っていることを感じます。

協力しながら。

2つ、3つと椅子を重ねて持とうとする辺り、好奇心と興奮と、半々といったところでしょうか。
「あんまり無理はしないように。」その都度丁寧に声をかける山下先生です。

いつもは子ども達(すいすい組(5歳児クラス))だけでやるテーブルにも、すっと入り、安全に行えるよう配慮します。

次は〝ほうき〟。
一連の流れを知っている子がいますね。次に何をするのかがわかる為、こうして自分のものを確保しようと先手を打とうとします(笑)

山下先生「ほうきを持ってない人—?」

子ども達「はーい…。」

山下先生「さて、どうしたらいいでしょうか。」

子ども達「終わったら貸す。」「順番に使う。」
山下先生「正解です。それともう一つ、椅子を運ぶ時もそうだったけど、これからほうき、雑巾と取り掛かる上で大切なことがあります。わかる人?」
「ケンカをしない」「仲良くやる」
どれも正解のような答えに頷きつつ、山下先生が口を開きます。

「あちらをご覧下さい。」

「にこにこ組(2歳児クラス)さんがもう寝ています。
「楽しいのはわかる。そして、近くで寝ている子達がいることをわかって、静かにやれるようになろうね。」
12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2015年3月5日『他人を察する』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)
〝「対人知性」と呼ばれる知性が、生きていくうえで最も大切だと言われています。この能力は、他人との関係性を築く力ですが、いわゆるコミュニケーション能力と言われるような、人と人とが言語によって会話をするとか、自分の考えをきちんと主張するという力ではなく、他人を理解する能力をいいます。(中略)
対人知性の本質は、「他人の気分、気質、動機、欲求を選別し、それに適切に対応する能力」と言われており、言葉によらない他人とのコミュニケーションであるともいえます。どうしても、言葉が話せるようになると、言葉で表現したもの、文字で表現したものから他人を理解しようとします。しかし、相手に対しての対応は、言葉では表さない心を理解する必要があるのです。〟
子ども達はこんな風にして、思いやりを学んでいくのですね。
さて、箒を手にした子ども達。この後どんな展開が待っているのでしょうか。
(報告者 加藤恭平)
最近、保育園における「騒音」が問題になっています。子どもの声がうるさいから保育園を建設しないでほしいという住民の声が…などの問題が報道されますが、本当に保育園はうるさい施設なのでしょうか。イメージとして「保育園はうるさい」と刷り込まれているということもあるのかもしれません。
しかし、子どもの声がうるさい保育園が存在するのも確かなのもしれませんね。それはその施設で行われている保育に問題があるのではないか、日本は子どものテンションを上げることばかりに意識があるために騒がしい保育園になってしまっているのではないかと以前、塾長が言われていました。
では逆に静かに、テンションを上げずに遊んでいるというのはどういう状況なのでしょうか。そのヒントは「会話の質」にあるのではないかと塾長は言われます。子どもたち同士が関わり、提案や受け入れを繰り返していれば大きな声にはならないのかもしれません。
そこで、園での子どもたちがどんな会話をしているのか調べてみることにしました。
短い時間ではあったのですが、今回はブロックゾーンでの子どもたちの会話を聞いてみることにしました。
まず「さあ聞いてみよう」と思いブロックゾーンにやってきたのですが、子どもたちの会話が聞こえないのです笑
あんまり接近しても不自然かなと思ったのですが、もう振り向くと私がそこにいるくらいまで接近してやっと聞こえるような声でした。この時点で、子どもたちがテンションを上げて大きな声で話しをしていないということを感じることができました。
次に、感じたのが、4つほどの島に子どもたちが分かれてブロック遊びをしていました。1つの島に2〜3人という人数でした。
それぞれの島では、動物園作り、列車を含めた街つくりなどが行われていたのですが、そこで行われていた会話の一部を紹介します。
「これいる?」
と男の子が動物園つくりをしている女の子2人組の所にブロックを持ってきました。男の子としては遊びの中に入りので、そういったアプローチをしたという感じでした。
そんな男の子の提案に1人の女の子が反応します。
「どれ?」
と言って、一瞬、男の子のブロックを見た女の子は続けて、
「いらない」
と一言。
無念にも女の子に男の提案は受け入れてもらえませんでした。
しかし、男の子は諦めません。
すぐさま。
「お届けもので〜す」
と言って、また違うブロックを持ってやってきました。
なんとか遊びの中に入ろうとしていました。
しかし、変わらず、女の子は…
「いりません」
ここで、男の子はアプローチの変えます。
「サンタクロースさんからですよ〜」と相手が気をひくような言い方に。
それを受けて、女の子は、
「サンタクロースさんにいらないって言ってください」
どうやっても男の子は遊びの中に入れません。
しかし、男の子も諦めません。
「おかしやエンピツはいりませんか?」
ブロックをおかしや鉛筆に見立て、遊びの中に入ろうと試みました。
それを受けて女の子が返した言葉は…
「動物園にはいりません」

ついに男の子は諦めて、女の子たちの遊びの中に入ることはやめていました。
しかし、男の子はその事に対して落ち込むということはなく、まして、女の子も意地悪だから入れてあげないということではなく、こういったことは、子どもたちの中ではよくある関わりだと思います。
私がブロックゾーンで子どもたちの様子を見ていたのはほんの5分ほどでした。
その中での一部のやりとりなので、まだまだ参考にはならないかもしれませんが、
このような会話を子どもたちが繰り広げていました。
今回は「提案とお断り」という感じの会話といえばいいのでしょうか。
こういった会話をしている子どもたちというのは決して大きな声をあげてはいませんでした。
本当に囁くように声を出しています。それは目の前にいる相手に伝わればいいからなのかもしれません。逆に近くにいる相手に話しかけるような遊びをしていれば大きな声を出す必要はないのかもしれません。人数が増えればその分の子に伝えなければいけないので、多少声は大きくなるかもしれませんが、それでも伝えたい相手ははっきりしています。ですので、部屋中に聞こえるような大きな声を出す必要はなくなりそうです。
「会話の質」ということに注目したことがなかったので、こういった見方で保育をみることもできるんだ!と新しい視点を塾長に教えていただきました!
もう少し保育園での子どもたちの会話を丁寧に調べてみたいと思います。
報告者 森口達也
一ヶ月程前のある日。

打ち合わせをしているのはすいすい組(5歳児クラス)の子ども達です。
この日は予てより楽しみにしてきた〝芋掘り〟の日!西武鉄道特急レッドアローに乗って〝埼玉いるま保育園〟を目指します。
ということは、、いよいよ彼らがデビューする日ですね!
臥竜塾生が更新しています当ブログ『生臥竜塾』2015年10月31日『伝承』というタイトルで塾頭山下祐先生が報告して下さっています。 (太字をクリックするとこの回の全文を読むことができます。)
〝先日、年長さんがお芋堀に行ってきたので保育園に残ったのはもちろん年中さんと年少さんです。朝のお当番活動の一貫で職員室と調理室にお休みを伝えにいくお仕事がありますが、今日に限っては年中さんが気合い入っていたようにも感じます。やはり年長さんがいない分、自分達がしっかりやろう!という気持ちが子どもなりにあるのでしょうね。〟
芋掘りへ向かおうとするすいすい組(5歳児クラス)の子ども達の一年前、らんらん組(4歳児クラス)だった頃に書かれたこのブログ。すいすい組(5歳児クラス)のいないこの日をきっかけに、らんらん組(4歳児クラス)の子ども達は憧れの〝雑巾掛け〟に取り組むのです。
すいすい組(5歳児クラス)という〝憧れ〟、ヒーローへの道のりを今まさに歩まんとするらんらん組(4歳児クラス)の子ども達。そんな彼らへそっと手を差し伸べるような温かな光景に、気付けばシャッターを切り続けていました。
(報告者 加藤恭平)
最後は3,4,5歳児クラスです。(以下太字のところが塾長の考え方)
新宿せいが保育園では、3、4、5、6歳児は一緒に生活しています。それは、ひとつには、個人個人の発達の連続性を重視するために、生年月日で発達を決め付けるのではなく、個々の課題によって活動を促すためです。

文字・数・科学ゾーン

ブロックゾーン

食事スペース①
たとえば、3歳児であってもはさみを使う能力は曲線切りができる子がいるかと思えば、5歳児でも、まだ、直線切りがやっとという子がいます。そんなときは、その子の課題は年齢によって決められるのではなく、個人の発達を理解し、把握をした上で課題が決められて行きます。子ども自ら、環境に働きかけるためには、その環境がその子の発達にあったものでなければなりません。そして、一人一人の子どもが自分の発達に見合った遊びやもの、人に自ら働きかけ、自発的に選べるために、大きな保育室に子どもの個人差の幅を受け止められる環境構成を用意していきます。

寝るスペース
また、異年齢児で触れ合うことも大切です。少子社会では、なかなか家庭や地域の中ではそういう機会が少なくなっています。異年齢児で遊ぶときには、様々な工夫が必要になってきます。それが前頭葉を育てることにもなります。また、発達が遅い子に教えたり、手伝ってやらなければなりません。そんな遊びの中から、子どもたちは様々なことを学んで行きます。また、そんな異年齢児とふれあいも大切だが、同年齢の子ども同士で関わることも大切ではないかとの質問を受けることがあります。しかし、このような心配は必要ありません。たとえ、異年齢児が同じ空間で生活していても、たとえばゲームをするときなどは発達のレベルが同じ同士でないと楽しくありません。同年齢で遊ぶことも大切なときには、子どもたちは、自然に同年齢同士で遊ぶことが多いのです。

制作ゾーン

食事スペース②

絵本ゾーン
子ども達が自発的に活動を選んでいく場合、動線には十分な配慮が必要です。活動をする場所とその活動に必要な材料が置いてある場所が離れていたり、異なった活動をしようとする子ども同士の動線がクロスしてスムースな活動を妨げたりするような動線は見直します。活動をするための場所とそれに必要な材料をおおまかなゾーンごとに区分けしておくことが大切です。
ちょうど2年前の2015年から、保育園の定員が115名から171名に増えた時に、保育環境を見直すことになりました。それまではワンフロアで3,4,5歳の遊びの空間を構成していましが、定員が増える事で2つのフロアを使って保育することになり、試行錯誤している当時の担任の姿を思い出します。
また実際に子どもの遊んでいる姿を見ながら少し環境を変えてみたり、それこそトライ&エラーの繰り返しです。そうしていく中で子ども達の活動と環境がピタッと合った時が落ち着く環境なのでしょう。
(報告者 山下祐)
2歳児クラスの重要性は塾長の講演でも言われています。また異年齢であるのに、どうして2歳児だけ単独なのか?疑問に思っている方もいらしゃるのではないでしょうか?(以下太字のところが塾長の考え方)
新宿せいが保育園では異年齢児保育が基本ですが、2歳児だけは例外的に単独で保育します。世界的に見てもこのような保育形態をとっているところは珍しいと思いますが、2歳児を単独で保育することには理由があります。

2歳児の「遊び」「寝る」空間
0~1~2歳の時期の発達の特徴は個人差が大きいことです。早い時期から歩けるようになる子どももいれば、なかなか歩き出さない子どももいます。でも遅かれ早かれいずれは誰もが歩けるようになります。一方、3~4~5歳の時期の発達の特徴は一人一人の生まれつき備わっているものや環境に大きく影響されることです。例えば手先が器用な子はその後も器用ですが、不器用な子が器用になることはありません。この場合の個人差は一人一人の個性であり、その先全員が同じ段階に到達することはないのです。

「食事」の空間
2歳児の時期は、誰もが遂げなければならない発達=生活の自立が完成し、個性の発達へと向かい始める準備期間なのです。また、2歳後半になっても生活の自立ができていないならば、なんらかの障害があることも考えられます。「障害がある子」ときめつけるためではなく、この先のケアの見通しを立てるためにも2歳児単独の保育が役立つのです。

食事の後に口の周りが汚れていないかチェックする鏡

ズボンを自分ではくための長椅子
また、この時期、みんなで一緒にいること、やることの楽しさをじっくり味わい、一方では、待つ、順番を守る、我慢するなど、耐性を身につける経験を重ねることも大切です。人と関わる力が育つ基礎になるからです。

自分たちで役割を決めての「ままごと」遊び
ちょうど私の息子が二歳児クラスです。確かに自分で出来る事が増えてきましたし、何よりも友だちとの関わりが多くなっているように思います。保育園から帰ってきて、「今日は誰と遊んだの?」と聞くとちゃんと「○○くんとあそんだの」「きょうは○○くんがおやすみだった」など友だちの事を教えてくれるようになりました。
一番の驚きは妻の出産をきっかけに二カ月ほど保育園をお休みしていたので、二カ月ぶりの保育園は絶対にぐずって行かないだろう・・・と覚悟を決めてお部屋に入ると、最初こそは照れてましたが、仲の良い友達の顔や先生の顔を見ると自然と部屋に行きました。それだけ息子にとって保育園という場は楽しく、過ごせる場だと親として安心しました。
(報告者 山下祐)
ちょっと急ですが・・・
もう一度、保育室の環境を見直そうと思い、塾長から以前に頂いた保育室の考え方をまとめたデータをそのまんま紹介しようと思います。
今回は0,1歳保育室です。(以下太字のところが塾長の考え方です)

ハイハイ~伝え歩きの赤ちゃんが過ごす空間
日本では0歳児保育室、1歳児保育室など生年月日による年齢別のクラス分けをあたりまえに行っています。でも、よく考えてみるとおかしなわけ方です。
今0歳児クラスにいる子どもは誕生日がくれば1歳になります。1歳になったら1歳児のクラスに移るのかというとそうではなく、翌年の3月までは0歳児クラスにそのままいます。ですから、寝返りをしている子と、その周りを走り回る子が一緒にいるようになってしまうのです。発達の個人差が大きく、月齢による発達の違いも大きいこの時期、便宜的に生年月日でクラス分けをするのは子どもの実情にそぐわないのです。
そこで新宿せいが保育園では0歳~2歳になるまでの子どもたちを、それぞれの子どもの発達の連続性を保障した空間で生活するようにしています。そして、遊ぶことと、食べることと、寝ることそれぞれの生活がきちんと個々の子どものペースで行うことができるように、保育室の空間は「寝・食・遊」の3つのスペースに分けられています。

「寝る」空間

「食事」の空間

「遊び(動のスペース)」の空間
保育室という空間は、子どもを収容する場所ではなく、子ども一人ひとりの生活の連続性を尊重し、発達の連続性を保障するような環境を確保する必要があるのです。

「遊び(静のスペース)」の空間

その時期の発達に合わせた手作りおもちゃ
実際に新宿せいが保育園に見学に来られた際に説明を受けたことがあると思いますが、こうして塾長の考えを文章で読むと、より理解が深まりますね。
またこの時期は入園前見学が多く、これから保育園に我が子を預けようと考えているお母さんお父さん方を案内させていただきますが、どうしても小学校のような年齢別のイメージが強く、異年齢という考え方が新鮮だったり、保育室も壁で区切られておらず、ワンフロアで保育をしている事に驚かれます。そういう親御さん達に自分たちが実践している「見守る保育」をどう伝えたら理解してもらえるのか?とても自分の勉強になります。またこうして塾長の考え方を見直すことで、自分の理解が深まります。
次は2歳児保育室を紹介したいと思います。(報告者 山下祐)

もちろん散歩にも行きます。

散歩先でも髪をとかしたり。
給食の時間も、

もちろん子ども達と。

中身は入っていませんが(笑)
子ども達から、「まりあちゃんの給食は?」と聞かれ、子ども達が余った食器で用意をしていました。食器がない時は、「せめて…」という感じでしょうか、お茶の入ったコップが置かれている光景をよく目にします(笑)
本物の給食が入っていないことを誰かが尋ねると、
「だってお人形だもん、食べられないでしょ?」
とのことで(笑)その辺りの線引きは子ども達もよく分かっているようです。
もちろんお昼寝もします。

と言うより気付くとこうしてお休みの子の布団に横になっているという感じです(笑)

まりあちゃんも。

気にかけてくれる子がいるからなのですね。

寝かしつけようとして、一緒に眠ってしまいました。
最後の写真の子は普段中々寝付かない子なのですが、この日はぐっすり眠っているようでした。
12年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2007年2月26日『ひいな』の中でこう書かれています。(太字をクリックすると藤森先生のブログ『臥竜塾』にとび、この回のブログの全文を読むことができます。)
〝人形遊びとか、ままごと遊びは、女子が、家事の所作を学んでいるといわれてますが、他にも、子どもにとって、癒し的効果のある遊びだったのかもしれませんね。だから、いつの時代でも、ままごとは子どもに人気のある遊びのひとつですし、最近は、男子も喜んで遊んでいます。きっと、癒されるのでしょうね。〟
これはひな祭り、雛人形についての考察のブログですが、この度の子ども達の姿ととても重なるものがあると思いました。子ども達はこのまりあちゃんとあんなちゃんにきっと癒されているのだろうと思います。
これからも一緒に楽しく生活をしていきたいと思います。素敵な場面に出会う度、これからもちょくちょく報告していきたいと思います。
(報告者 加藤恭平)