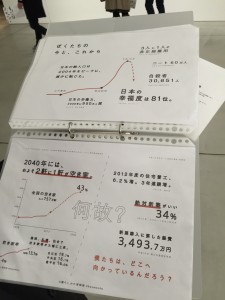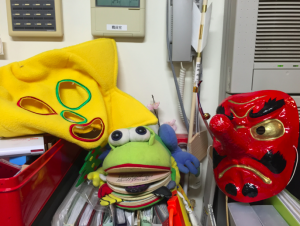〝箱根海賊船〟を後にして、次に訪れたのは、〝箱根☆サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム〟です。(詳しくはhttp://www.tbs.co.jp/l-prince/をどうぞ♪)

入場します♪

ほらまたあのポーズ!(笑)
正直なところ、僕は〝星の王子さま〟を読んだことがなく、なので、館内の説明員の方の説明で初めて内容に触れる、といった感じでした(笑)
しかし、とてもいいお話ですね。お土産に本を買って帰りましたが、帰り道でも読み切れる程の短さで、人生の真理を描きつつ、当時の人の人生観を表しているような、壮大な作品であると思いました。
〝心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ〟
作品を象徴する言葉で、文中に出てくる数々の名言の中でも特に代表とされる王子さまのセリフです。
このミュージアムの中に、作者サン=テグジュペリの幼少期を過ごした部屋や、作品を描いていた当時の部屋が再現されていました。
ふと西村先生が、「藤森先生の子どもの頃の部屋を再現しましょう」と(笑)
それぞれに色んなインスピレーションの湧いた見学となりました。
さて、一泊二日の旅行の1日目。時間もいい時間になってきました。〝箱根☆サン=テグジュペリ 星の王子さまミュージアム〟を後にして、バスに乗って一路、本日のメイン(?笑)であります、宿泊先へ♪♪

雰囲気がありますね♪

バスの急勾配・連続カーブでよもやダウンかと思われた小松崎先生を癒すかのように、いい風が吹いていました。

面白い川ですね。

本日の宿泊先〝天成園〟(http://www.tenseien.co.jp)に到着♪

心躍ります♪
チェックインを済ませ、早速お風呂へ♪
体を洗って清めた(?笑)後、藤森先生を囲んで塾生全員で数ある浴槽の一つに浸かりました。
温泉内は広く、外の露天風呂の一角に皆で入ったのですが、若林先生は中で迷ってしまい(笑)食事の時間も近付いていた為、若林先生が入った瞬間に皆あがるという(笑)何とも面白い出来事もありました。

とても開放的で気持ちのいい温泉でした♪(本多先生、顔…)
11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されています『臥竜塾』ブログ2013年10月1日『湯治』(http://www.caguya.co.jp/blog_hoiku/archives/2013/10/湯治.html)の中にこう書かれています。
〝私は、よく温泉好きといわれます。以前ブログで書いたと思いますが、私は高校生までは入浴は銭湯でした。育った地域の下町では、ほとんどの家庭は銭湯に通っていました。ですから、私は自分で好きな時に、一人でのんびりとは入れる家庭風呂にあこがれていましたから、ホテルで、小さくてもいいのでのんびりひとりで入れるバスはあこがれました。しかし、我が家で小さい風呂に入るようになってから、大きな風呂に手足を思い切り伸ばせることが楽しみになってきました。しかし、そうはいっても、温泉はそれほど好きではありませんでした。それは、「湯あたり」なのでしょうか、温泉に入った後、だるくなるからです。また、せっかく温まりたいのに、寒い中で入る露天風呂もあまり好きではありませんでした。
それが、年を取るにしたがって、疲れをいやすのに、温泉にゆっくり浸かることが効果的になってきました。ということで、最近は、講演などに地方に行くときには、終わったその晩は、ゆっくりと温泉に浸かって、のんびりすることにしています。そうすることによって、次への活力を取り戻そうとしているのかもしれません。そんな温泉の効果を感じます。〟
藤森先生は温泉がお好きなのですね。この回のブログには、温泉についての解説も書かれていますので、紹介させていただきます。
〝日経新聞に「ヘルスツーリズム 湯治現代風に復活 温泉+散歩で病気予防/観光との連携課題」という記事が掲載されていました。そこには、「日本に古くから伝わる“湯治”が、現代の生活様式にマッチした“ヘルスツーリズム”としてよみがえろうとしている。ドイツを手本に、温泉やウオーキングで疾病の緩和や予防につなげる健康保養地作りに取り組んだり、温泉に滞在して療養する人の費用を補助する自治体もある。宿泊や飲食など地域の活性化への効果を期待する声がある一方で、定着には医療と観光の連携など課題もある。」
確かに、日本には「湯治」という「温泉に入浴して病気を治療すること」という治療方法がありました。そして、その目的として、疲労を回復させる「休養」、健康を保持し病気を予防する「保養」、病気の治療をする「療養」の3つがあります。どこか体の具合がよくないときに、知識や医療の技術が十分に発達していなかった時代、その伝聞されていた効能に期待して、温泉に入浴したり飲泉するなど、多くの人が温泉療法によって病気からの回復を試みていました。
そして、明治時代以降、医学の近代化が図られて西洋医学が中心になっていくのですが、湯治の近代化として滞在型温泉療養施設の建設がドイツのエルヴィン・フォン・ベルツ博士から提案されています。これは実現しませんでしたが、いくら医学が発達しても、江戸時代に定着していた湯治文化はすぐに廃れることはなく、細々でも続いていました。
一方、ドイツでは「クアオルト」という「健康保養地」というものがあります。これは、温泉や気候、海といった自然の力を活用し、予防や治療をする地域を指します。(1)病院などの治療施設(2)専門医(3)交流施設(4)滞在プログラムがあるという条件で、州がクアオルトを認定しています。そして、医師が処方すればクアオルトでの治療が保険の対象になるそうです。ドイツには、2007年統計によると、計374カ所(2007年)あるそうです。〟
温泉の良さを改めて感じます♪
そしてお待ち兼ね…

食事は豪華なバイキング♪

〝食事〟という名の幸せな戦い、聖地に乗り込む勇者達の後ろ姿です
なんとも美味しいお食事でした♪中でも、本多先生はデザートのチョコクッキーを、塾頭並びに塾生は、もずくを好んでそれはそれは大量に食べました(笑)西村先生はデザートを挟んでから、カレーを食べるという奇行を(笑)西田先生はそんな西村先生を「アンダー25はすごいね」と言いつつ、デザート後に焼きたてステーキの列に並ぶという、なんともアグレッシブな食事の時間となりました。
「黒烏龍茶があるから大丈夫です♪」「黒烏龍茶でプラスマイナス0です♪」と笑顔で語る西村先生と若林先生を見て、とても応援したい気持ちになり、このブログと出会うことができましたので、最後に添えさせていただきます。
『臥竜塾』ブログ2014年8月5日『無力状態』(http://www.caguya.co.jp/blog_hoiku/archives/2014/08/無力状態.html)の中にこう書かれています。
〝病気になるのは、生まれつき自分は弱い体質であり、遺伝的なものであると多くの人が思っていますが、実は、自分たちが考えているよりもずっと、自らの肉体的健康をコントロールする力を持っているものだとセリグマンは言います。健康について、「私たちの考え方によって健康状態が変わる」「オプティミストの方がペシミストよりも感染症にかかりにくい」「オプティミストの方がペシミストよりも健康的な習慣を持っている」「オプティミストの方が免疫力がある」「オプティミストの方がペシミストよりも長生きであることが証明されている」
日本では、「病は気から」という言葉があり、その註釈には、「心配事や不愉快なことがあったりすると、病気になりやすかったり、病が重くなったりするものである。気持ちを明るく持ち、無益な心配はしないほうが、病気にかかりにくかったり、病気が治りやすかったりするということから。」とあります。まさに、昔から同じことが言われているようです。〟
二人の考え方はまさにオプティミストそのものではないでしょうか。
健康で長生きをして、いくつになっても皆で集まって旅行に行ったり、楽しい話をしたりしたいなぁと改めて感じた夜でした。
(報告者 加藤恭平)