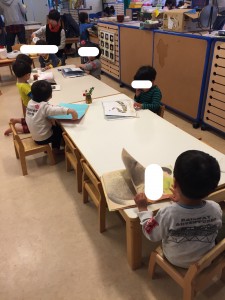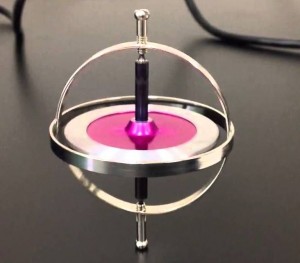1歳児クラスでの出来事です。
皆さんは、昼寝から子どもを起こすとき、どのように起こすでしょうか。もちろん、子ども自らが気持ちよく目覚めてくるというのが理想ではありますが、なかなかそうはいかないこともあります。保護者から「最近、就寝が遅いので、昼寝を短くしてくれませんか。」等という要望もあって、個別対応することもあるからです。もちろん、その子どもの体調を考慮して起こすのですが、そんな時は「◯◯ちゃん起きて〜!」「おはよう〜!」と何度も声をかけたり、体を揺すったりします。しかし、なかなか起きてくれません…。
先日、Aちゃんを起こそうとしました。一度起きたのですが、再びマットに寝転がります…笑。他の子の布団を片付けながら、遠くからその子に声をかけていました。すると、その声を聞いて、既に起きている子どもたちが行動したのです。
数人が集まってきて、「おーきーてー!」「みーなおきたよ(みんな起きたよ)」等と言いながら体や頭をさすったり、背中を叩いたりします。
初め、Aちゃんは無反応でした。しかし、他の子どもたちが自分に対して何か言っていると分かったのか、ムクムクっと動いたりします。その姿を見たある子どもが、急に「きてねー!」と言って部屋の方へと走って行きました。
すると、別の子どもも「きてねー!」「こちだよ(こっちだよ)ー!」と言って、みんなが別の部屋に行く空気感を出して、Aちゃんを呼び込もうとするのです。
Aちゃんは、その姿を顔だけ起こしながら眺めていますが、まだ体を起こそうとはしません。そんなAちゃんの姿を見て、走り去っていく雰囲気を出した子どもは首を傾げてこう言いました。
「あれ?」
それにつられて別の子も…
「あれ?」
この方法なら来てくれるだろうと思っていたのですかね(笑)。
仕方がないので、リターン…。元に戻ってきて、再び「おきてー」攻撃です。いつの間にか人数も増えています(笑)。
すると、徐々にAちゃんに変化が現れます。うつ伏せ状態で、上半身を起こしながら笑顔を浮かべています。5人で取り囲んで、なんとか起こそうとしています。「みーなおきたよ、みーなおきたよ」「おーきーてー」と言っています。そんなやり取りの中、Aちゃんの反応を見て、“これはいける!”と思ったのか、もう一度「きてねー」作戦を試みるのです。
一度ダメでもあきらめないところがいいですね。
一人目が走り去り…
二人目が走り去り…
三人目が走り去ります。
…数秒後、ついにAちゃんが動くのです。
ゆっくりと腰を上げ始め…
立ち上がり…
笑いながら小走りでその子どもたちの後を追いかけて行くのです。
また“小走り”といったところがいいですよね(笑)。先にある“楽しさ”や“面白さ”に体が反応しているかのようです。
そして、Aちゃんが本当に起きて来たことを知って、走り去っていったある子どもは「うわぁ〜!!はははっ〜!」と笑っていました。その言葉の中には、嬉しいのと、驚いたのと、楽しいのと、喜んだのと、様々な感情があったのではないでしょうか。
何がAちゃんを動かしたのでしょうか。何度も誘ってくれた事に対する誠意や協力でしょうか。それとも、楽しそうな雰囲気でしょうか。起こす人が私であれば、Aちゃんはまだ寝ていてもおかしくありません。その子を早く起こそうとする大人が、言ってみてもそうならないのに対し、子どもたちが楽しそうに“こんな方法で?”といった様々なやり方で起こそうとした方が、結果的にスピーディーに事が運んだという事実がありました。
私は普段、子ども同士を結び付けようとあれやこれやと考えたり動いたり言葉がけをしようと心がけています。しかし、子どもたちはこのように、既に結びつき合って関わり合っています。他児の気持ちを理解しようと、一つ一つの反応から次の自分の行動を考えています。つまり、私たちがそれを妨げない限り、子どもたちは自ら結びつこうとしていることがわかりました。私たちが必要なのは、あれやこれやと環境を考える前に、既に目の前にある、子ども自らが求める子ども同士の関わりを「妨げない工夫」であるのだと感じました。
(報告者 小松崎高司)