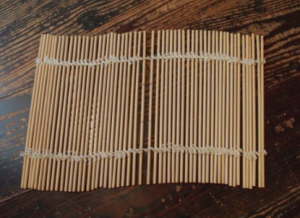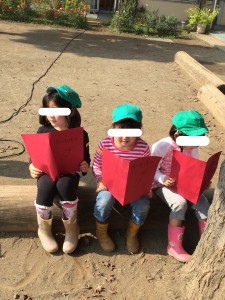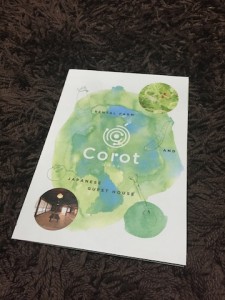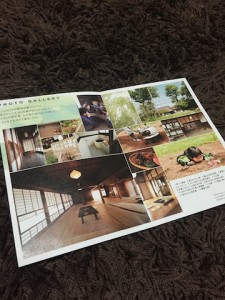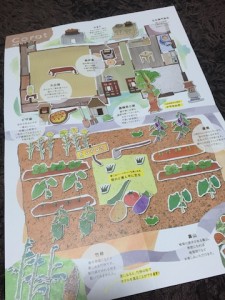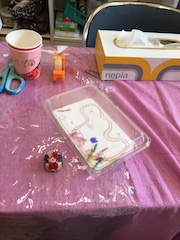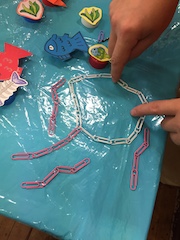先日の土曜保育の時間に感動したことがありました。
その日は、我らが誇るベテラン男性職員が午睡前の紙芝居を読んで下さいました。
ナスのお化けが出てくる紙芝居で、子ども達は〝オバケナス〟と覚えて、とても印象に残った様子で布団へ入っていきました。
にこにこ組(2歳児クラス 以下にこにこ)担任の僕も、午睡の場所へトントンをしに行きました。
リズミカルにテンポよく、ビートを刻みながらトントンをしていると、にこにこの男の子が急に、
「このズボン嫌だ。」
と言うのです。どうやら寝る時になって今履いているズボンが気に入っていなかったことを思い出したようなのです。子どもってこういうところ、ありますよね(笑)
にこにこの部屋に行って履き替えてくることに。ところが着替えの引き出しの中には、お尻にポケットがついた、これまた彼のお気に入りではないズボンしか入っておらず(笑)嫌がりながらもしぶしぶ納得させ、その時は彼の承諾もきちんと得て、そのズボンに履き替えて、また布団へ戻りました。
布団へ行くと、ぐんぐん組(1歳児クラス)の今年入られた大型新人の一人であり(僕は新人の方全員大型新人だと思っています)、3児の母であり、この度の主役である先生がトントンをして待っていました。その先生の顔を見て、「この先生なら…」と思ったのでしょう、(このあたり、子どもの対人知性の一つだと感じます)
「このズボン嫌だ。」
と、本当は嫌だった心の内をその先生に伝えていました(笑)
僕は、もう他に彼のズボンはないし、あとは保育園のズボンを貸すことくらいしか思いつかず、そのことをその先生に伝えようとした瞬間、なんとその先生は、彼のお尻のポケットを優しくキュッと掴み、
「これでもうポケットはなくなったよ。もう大丈夫だから寝ようね。」
と優しく諭したのです。
コクンと頷き、納得した表情で布団に入っていく彼を見て、その先生の鮮やかで優しく、温かみのある保育に、とても心を打たれてしまいました。
11年目に入られました藤森先生が毎日欠かさず更新されているブログ『臥竜塾』2013年10月25日『教師から教育者』というブログの中で、こう書かれています。
〝私たちは、教師というとどのようなイメージを持つでしょうか?「教える人?」「偉い人?」「権威を持った人?」「権力を持った人?」「怖い人?」「優しい人?」様々な印象を持っている人がいるでしょう。その多くは、自分が出会った教師のイメージがあるかもしれません。また、それは、時代によっても変わってきているかもしれません。(中略)
ペーターセンは、教育者と生徒の関係、また、生徒と生徒との関係は、「人間的なもので、より高貴な基本的な態度に基づくべきである」と言っています。〟
より、高貴な基本的な態度。それは、見守る保育の三省の中にもある、
・子どもに真心を持って接したか
という基本姿勢であると同時に、その人それぞれのもつ愛情そのもののようにも思えてきます。
また、『臥竜塾』ブログ2013年5月21日『偉大な旅6』の中で、
〝ある出来事が起きたときに、男女という違う脳を持った存在が補い合い、生きていく知恵を生み出していくのです。(中略)そして、様々な年齢差を持つ集団も、遺伝子を次世代につないでいくために必要な多様性のひとつです。〟
とも書かれており、ズボンを履き替えることしか思いつかなかった僕を、そっと優しく、まるでお母さんのような愛情で包んでくれたその先生の保育は、まさに多様性の部分を体現され、僕の足りなさを補って余りあるものでした。
その職場での経験年数でなく、人生を積み重ねてきた人のもつ器量や懐、そういったものが、人それぞれの中に必ず存在します。このような先生が存分に腕をふるえるような、その人らしさが自然と出せるような環境を、僕は本当に素晴らしいと感じます。
感動は続きます。その子が眠るまでのもう一つのドラマを紹介して、この度の報告を終わらせていただきます。
(報告者 加藤恭平)