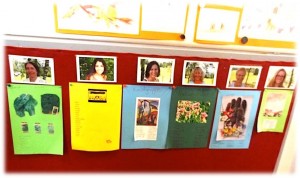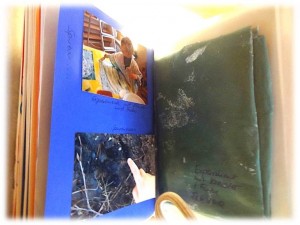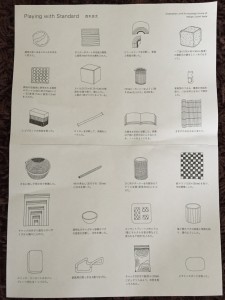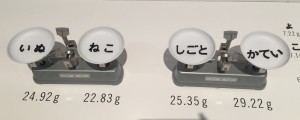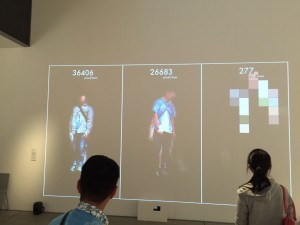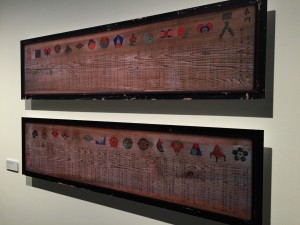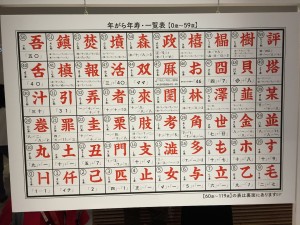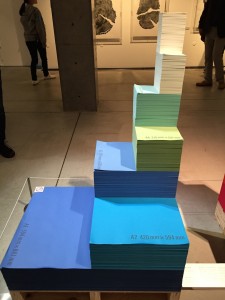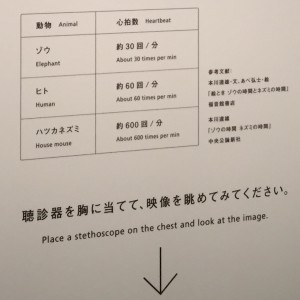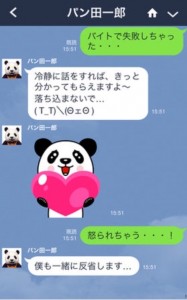一か月ほど、まえの話になりますが、私の幼稚園の園長先生と園の職員とで熊本にありますGT園に見学に行かせていただきました。というのも、今後、私のいる幼稚園は認定こども園になるにあたり、保育の形態を異年齢やチーム保育に変えていくことになり、そのため、保育の考え方も今までのものではなく、新しい方向に変えていくことが必要ではないかということで、「見守る保育」の形を考えていこうということになりました。ただ、これまでこの保育をやっている園が保育園ばかりで、幼稚園の職員は「幼稚園でどう変えていったのか知りたい」という要望が多いので、そこで、GT園の先生にお願いして、今後の見学のために、下見という形で行かせてもらうことになりました。
幼稚園でいかに「見守る保育」を行っていくことができるのだろうか、幼稚園という特質をいかに活かして、子どもたちの保育を進めていけるのか。ひとつの特徴としては大体の幼稚園は保育園に比べ、3~5歳児の子どもたちの人数が多いところが多いということです。異年齢にするとしても、一グループでは人数が多いので、いくつかのグループを作らなければいけないことなど、子どもの人数に対して、どう保育を組み立てていくのかということがありました。
そこで例えば、いくつかの質問がありました。
Qグループの環境をどう作っていますか?
A グループごとでテーマを変えて環境を作るようにしている。また、各グループで必ず使うもの(製作・パズル・ままごと)をおいていますが、グループによって、そのゾーンを大きくして、Aグループはままごとのおもちゃが多くある。Bグループは積木がある。など、グループだけで完結するのではなく、特徴を作り、グループ間の子どもたちも交流をできるようにしている。
Q.発表会などはどうしていますか?
A.人数が多いので、2日に分けて行っています。劇は年齢別(言語発達や表現を見せるため)、ダンスや楽器はグループごとでやっています。
Q.各クラスのカリキュラムはどうなっていますか?
A.子どもたちが主体的に活動することを目的にしているので、がっちりとカリキュラムを作るというよりは子どもたちの環境を整えて、選択制をすることで子どもたちが発達にあった活動ができるように工夫している。
などなど、いろんな質問に対して言葉をいただきました。
見学園の先生のアドバイスはとても刺激を受けますね。一緒に下見にいった幼稚園の先生も、グループの作り方、環境構成の工夫、行事や保育の考え方の転換など、自園だけで話し合ったり、提案を聞くだけでは、頭で理解していても、それをいざやるとなるとどこから手を出せばいいかわからないということがあり、なかなか実践にいたるまでに至らないことがあります。実際に園を見学させてもらったことで、少しずつ想像がついてきたようです。やはり「百聞は一見に如かず」ということですね。今後は他の幼稚園の先生も見学にいくことで、よりこの流れを大きくできればと思います。
また、その時に姉妹園の保育園さんも見学させていただきました。どちらの園も、実際、新宿せいが保育園での実践をすぐに取り入れ、環境に活かしている様子を見ていると自分自身ももっと行動力を付けないといけないなと思いました。こういったつながりができることはとても心強いですし、楽しかったです。なにより、私の場合なかなか会えない外部塾生同士のかかわりができたのが、とても一つの大きな収穫でした。
(投稿者 邨橋智樹)