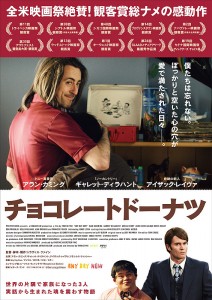先日、塾長の提案から【スマイルミッション】という企画に参加しました。簡単に説明すると、子どもたちがメッセージカードに思いを表現し、そのカードを持っているみんなの写真を宇宙へ飛ばし、自分の分身が宇宙旅行をするといった企画です。宇宙という、まだ未知で壮大なものを身近に感じられる、素晴らしい企画です。
メッセージカードが送られてきた封筒の中には、宇宙クイズの紙も入っていたので、子どもたちと職員とで楽しんでいました。例えば、羽を広げたような写真でよく見る「国際宇宙ステーション(ISS)の大きさはどれくらいでしょう?」とかです。子どもも大人も予測しながら答えを考え、解答を見てみんなで驚いていました。
今回、そのような導入を経て、メッセージカードには「自分の夢」を書いてもらいました。各々、自分の夢を絵や文字で表現していきます。子どもたちは、「アイドルになりたい」「エルサになりたい」などと表現していく中、個人的に気に留まった夢が描かれてありました。
私は、子どもに将来に希望を持って生きていてほしいといった願望があります。それはきっと、大人なら誰しもが思い描いていることでしょう。そのため、普段、職員間での楽しい話を子どもの前でも話すようにしています。そして、最後に必ず「はぁ〜、大人って楽しいなぁ」と言っています。それはそれは非常にわざとらしく聞こえてしまいますが、本音でもあります。もちろん、子ども時代が楽しくないといった事ではなく、大人になること、大きくなるっていうことに対して、積極的で夢のある楽しいことである事を感じてもらえたらいいなと思っているのです。子どもには笑顔で接し、職員間ではただの無表情の業務連絡だけが飛び交っている状況は不自然ですよね。
そんな個人的な思いが、偶然かもしれないのですが、今回「オトナ二ナリたい」という形で表現されたことを、勝手に嬉しく思ったので報告させてもらいました。
街中や電車内で、見ず知らずの子どもと目が合うと、大人はどうしてその子どもに対して笑顔を見せるのでしょうか。自然に笑顔になってしまうという人もいれば、違った理由もあるかと思いますが、きっと「この世界は楽しいよ」「これからが楽しみだね」と本能的に伝えようとしているようにも映るのです。
以前、塾長のブログに“未知な部分、わからない部分にロマンを感じる”などと書かれていたことを思い出しました。子どもにとって、大人というのは近くにいながらも「未知」なる部分でもあるはずです。そんな大人にも、身近で大きな「ロマン」が詰まっているのだと思います。
(報告者 小松崎高司)