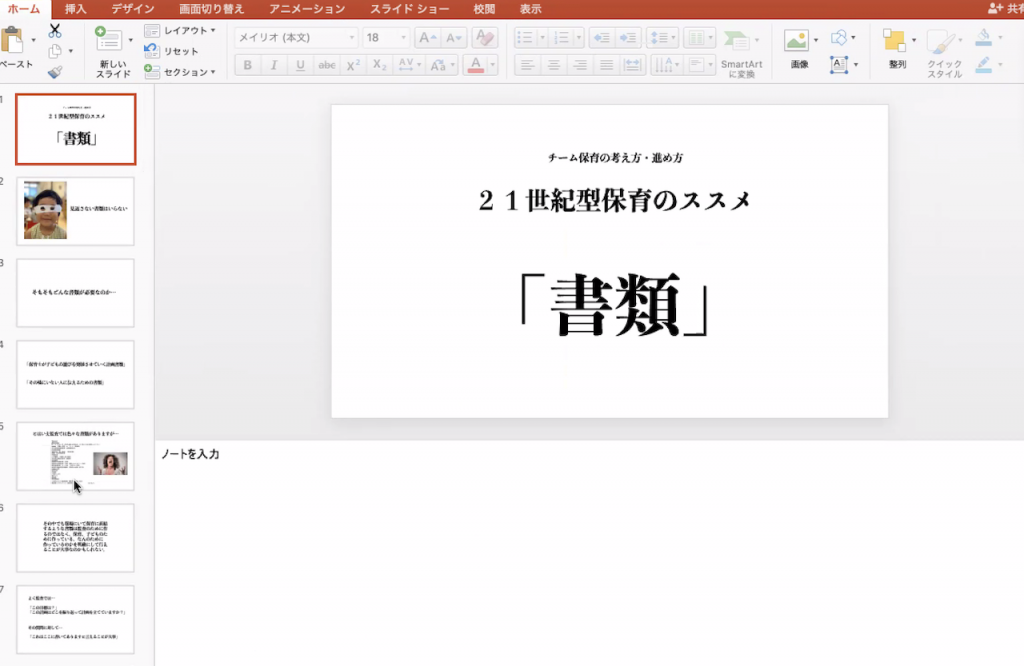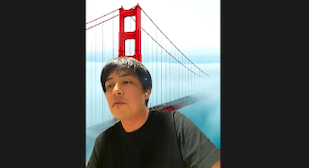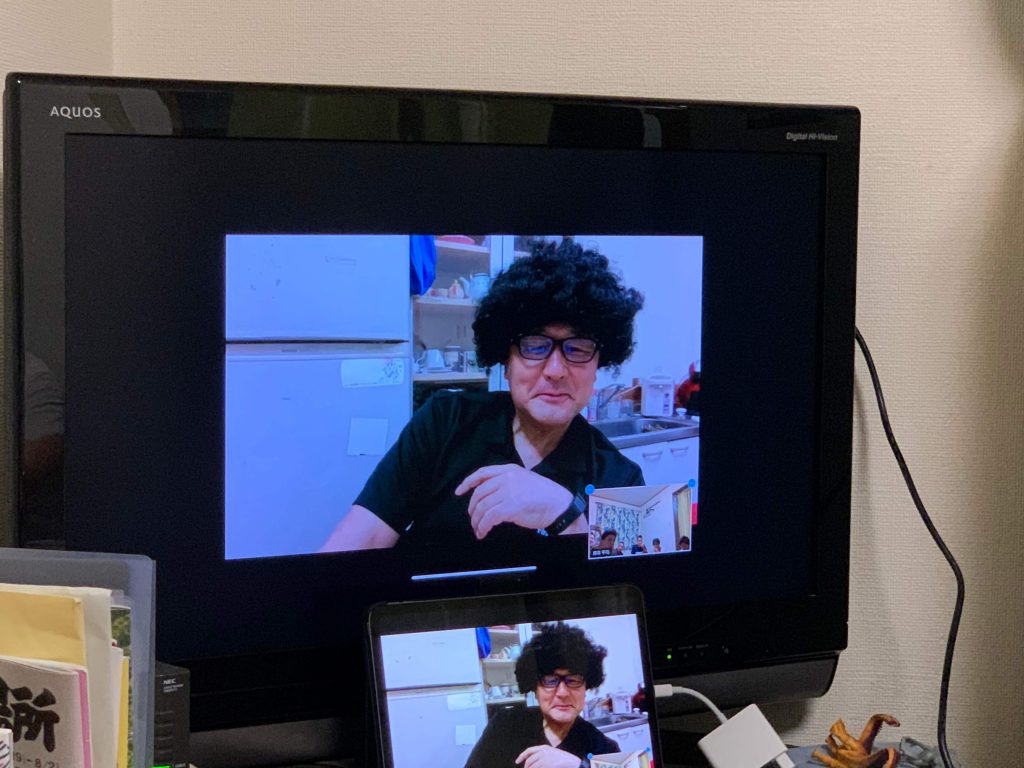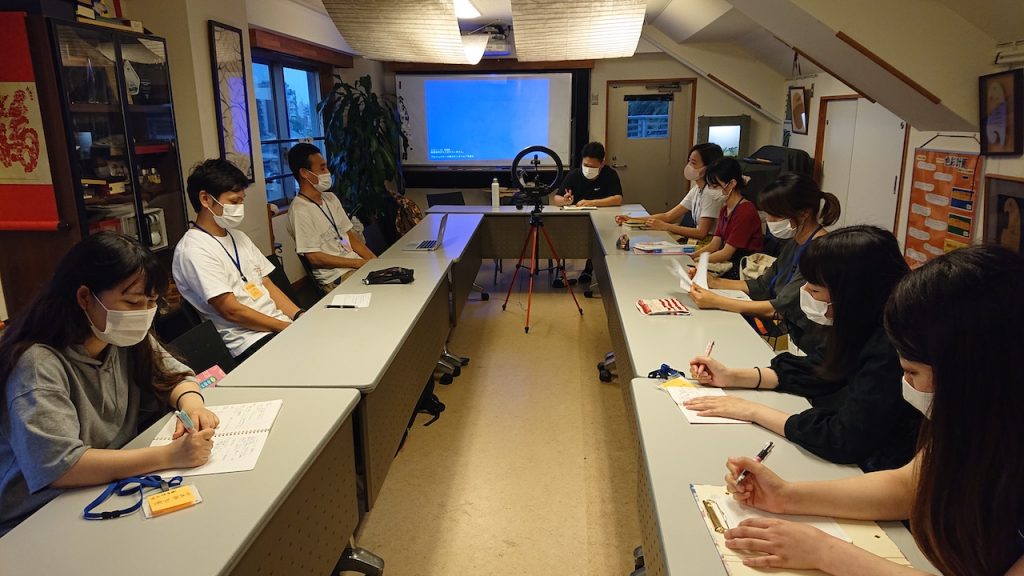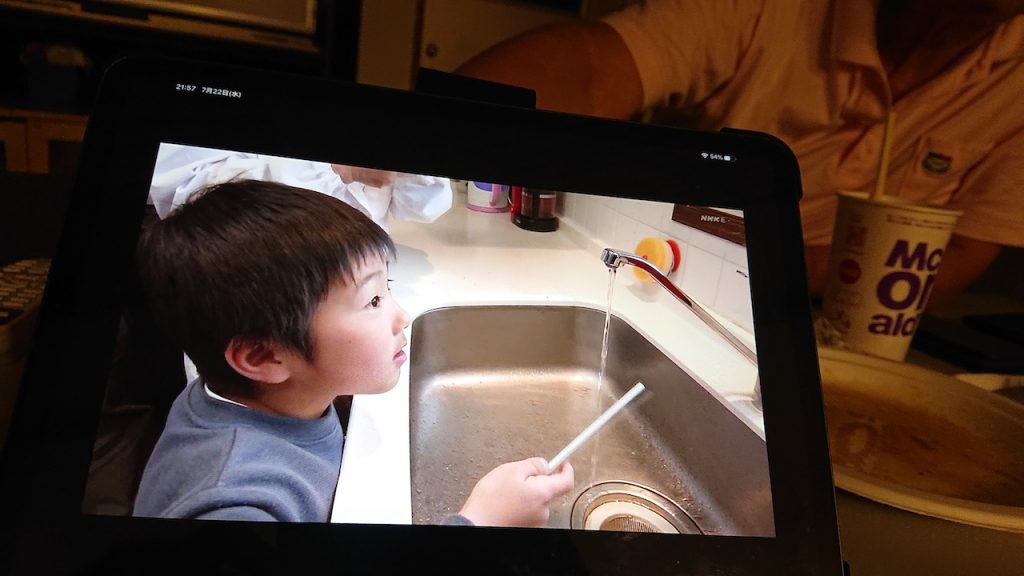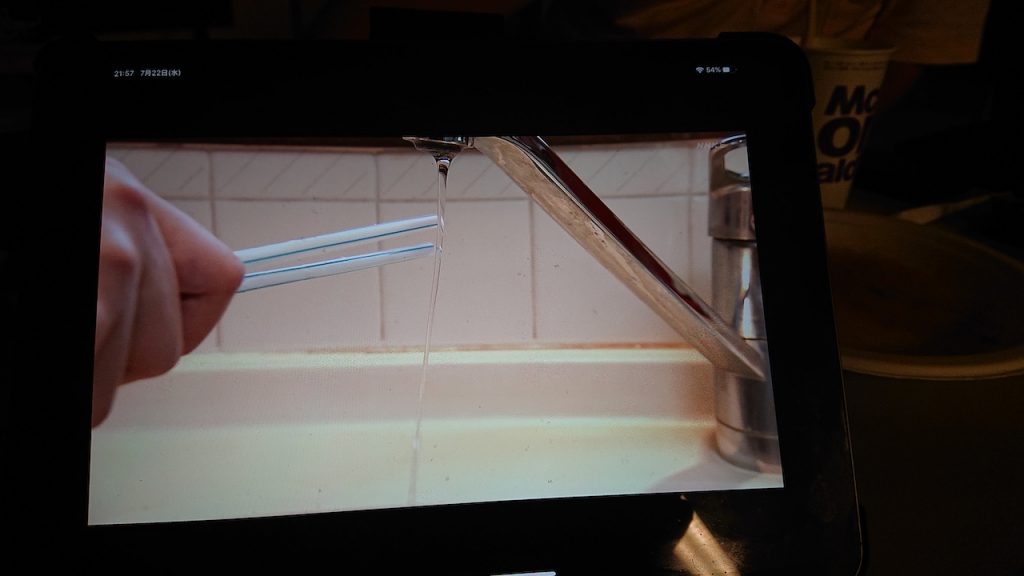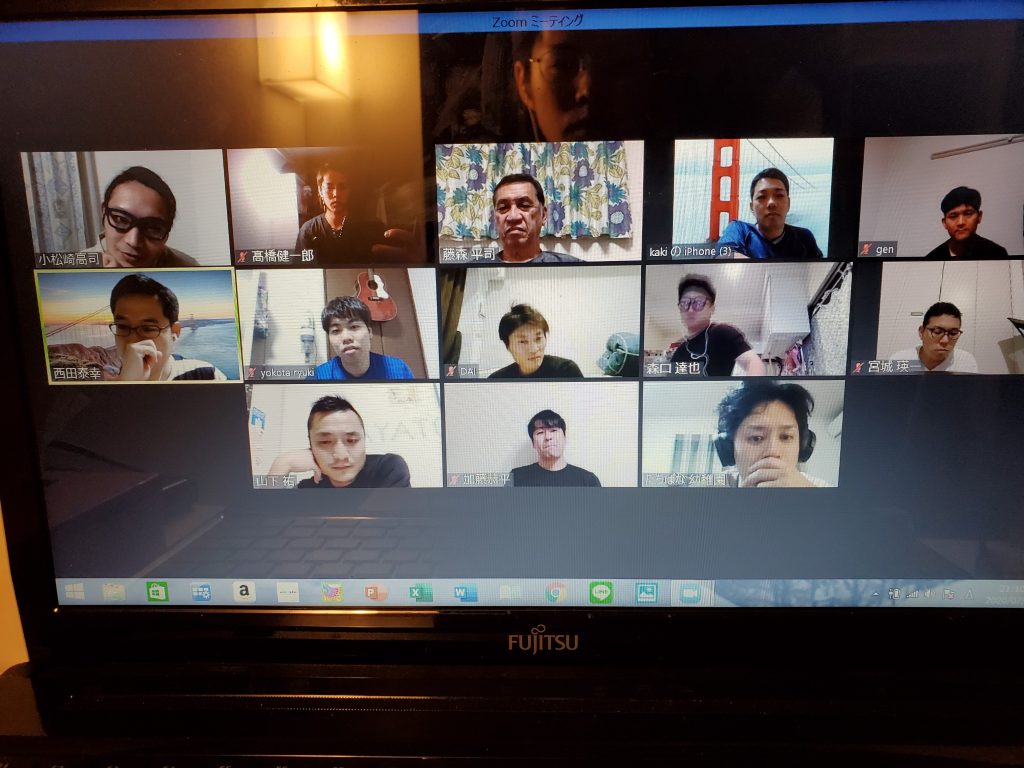少しずつ日本列島にも台風が到達する時期になりはじめましたね。台風12号も関東に直撃するかと思いきや、なんとか思い止まってくれたようで、ほっと胸をなで下ろしています。
皆さんは台風と聞くとなにを思い浮かべるでしょうか。今回の12号がドルフィンであるように、一つ一つに名前が付いていることでしょうか、それとも一瞬の晴れ間を映し出す台風の目についてでしょうか。わたしが台風が近づいていると聞いて一番に思い浮かべたのは『バタフライ効果』についてでした。
それでは9/23の塾報告です。
今回は台風の影響もあり荒天ということでズーム開催となりました。やはりズームでやると全国各地の先生の姿を見ることができるという、ズームならではの良さに毎回心が踊ります。

今回は、これから臥龍塾で企画していることや、確定していないことが多く、あまり詳細な報告はできないので、そんな話を聞きながらわたしが考えていたことについての報告とさせていただきます。
まず、冒頭のバタフライ効果とはなんだ?となった方もいらっしゃるかもしれませんが、バタフライ効果とは、遠くで起きた小さな事象が、全く別の地の遠い先の時間に大きな影響を与える、ということを、『ブラジルではためいた蝶が起こした風が、テキサスでハリケーンを起こす』といった気象学者であるエドワード・ローレンツの言葉から産まれた現象です。
今回の塾でわたしの中に強く残った部分として、
コロナが流行している今の時期に、オンラインなどで必要な情報を配信する媒体に需要があることは誰しもが理解していることだが、果たしてその需要に答えられるのか、どう向き合っていくべきなのか、そして、その需要を満たした先の新たな需要にどう繋げていくのか、というものがありました。
最近行事リーダーをしていると、保育中でも他の先生方が隙間を作ってくださり、行事関連の仕事をさせてもらうことが多いのですが、自分がいなくても滞りなくまわっていくクラスの日常に、安心するような、でも少し寂しいような不思議な感情を覚えます。
自分という存在は組織にとって必要であっても不可欠ではありません。ならばどうすれば自分は不可欠になれるのか、自分への周囲の需要はどのようなものなのか日々考えることは、保育の質の向上にも繋がっていきます。子供にとって今時分が必要なことはなにか、時には関わり、時には一歩引き場を整える。そんな目を今養っている最中であることを行事を通して感じさせられます。
少し話はそれましたが、今現在のコロナ禍の需要に答えるということは、まさに今起こす小さな一歩が、未来に大きな影響を与えるという良い例ではないでしょうか。
今新宿せいがこども園がやろうとしていることが小さなこと、というわけではありませんが、今始めたことがいずれ大成し、世の中により大きな影響を与えていくと考えれば、これほど楽しみなことはないのではないでしょうか。
“思い立ったが吉日”なんて言葉もありますから、常日頃から行動力は持ち続けていたいですね。
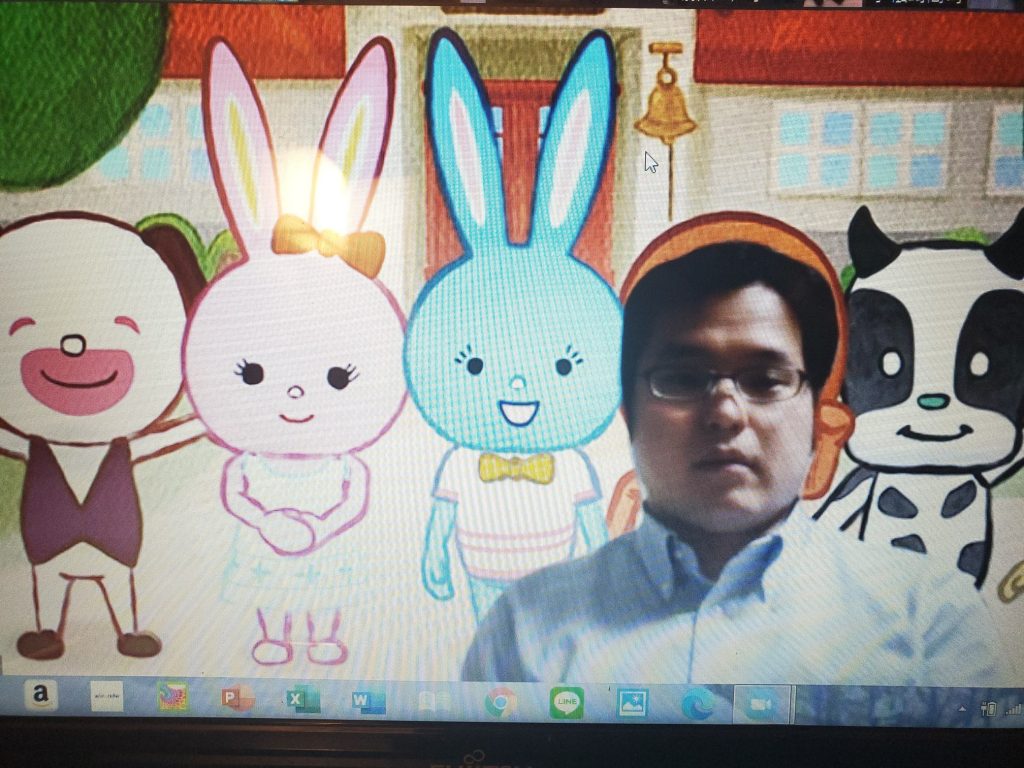
日々学ぶことができるこの環境に感謝しながら報告を締めさせていただきたいと思います。
(報告 髙橋)