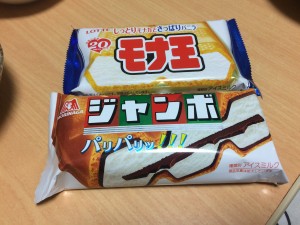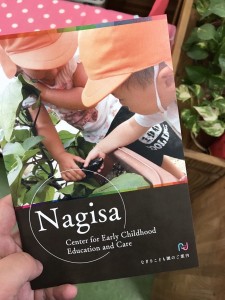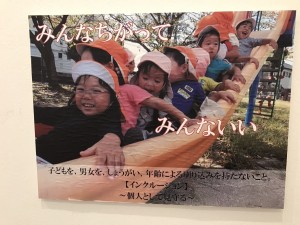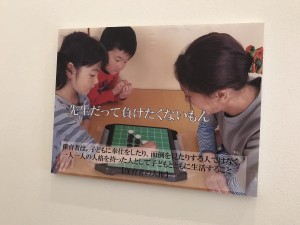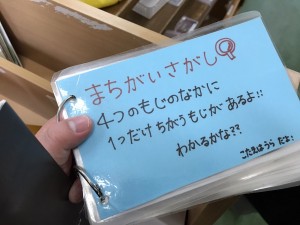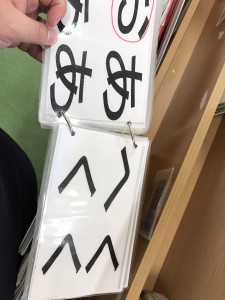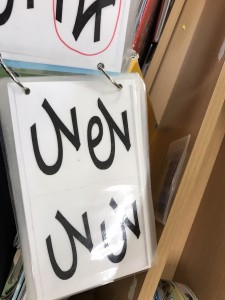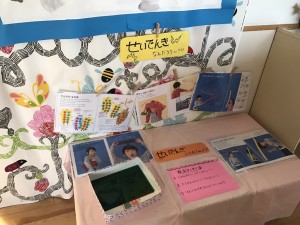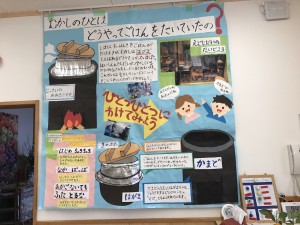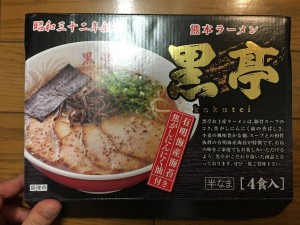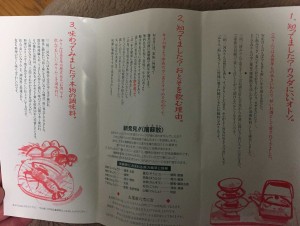4月4日臥竜塾報告をさせて頂きます。
前回、田崎先生のブラヘイジ報告が途中だったので、その続きが今回聞けました。しかし、その前に今年の臥竜塾セミナーの日程をみんなで決めました。GTメールでも流しましたが、以下の通りです。
4月25日(火) 文字
5月23日(火) 数
6月20日(火) 科学
7月25日(火) 文字
9月26日(火) 数
10月14日(土) ブラヘイジ
11月21日(火) 科学
12月19日(火) 文字
1月23日(火) 数
2月27日(火) 科学
以前にも報告であったと思いますが、今年のテーマは「文字・数・科学」です。
最近の塾長の講演にもつながる話で、セミナーでもお話するので、ここでは詳しくは書きませんが、学力の3要素や、幼児期に育む10の力などから文字数科学を考えていこうと思います。(まだ、私自身話すことがまとまっていないので、こんな簡単な報告になりました)
では、田崎先生のブラヘイジ報告の続きです。
杜子春の話で終わっていたと思いますが、そういえば…と他の先生が思い出したのです。ちゃんこを食べて、杜子春の碑を見る前に、回向院というお寺の見学に行きました。このお寺は、今から約360年前の明暦3年(1657年)に開かれた浄土宗のお寺です。この年、江戸には「振袖火事」の名で知られる明暦の大火があり、市街の6割以上が焼土と化し、10万人以上の尊い人命が奪われました。この災害により亡くなられた人々の多くは、身元や身寄りのわからない人々で、当時の将軍家綱は、このような無縁の人々の亡骸を手厚く葬るようにと隅田川の東岸、当院の現在地に土地を与え、「万人塚」という墳墓を設け、遵誉上人に命じて無縁仏の冥福に祈りをささげる大法要を執り行いました。このとき、お念仏を行じる御堂が建てられたのが、回向院の歴史の始まりだそうです。この起こりこそが、「有縁無縁に関わらず、人・動物に関わらず、生あるすべてのものへの仏の慈悲を説くもの」として現在まで守られてきたのが、回向院の理念だと、HPに書いてありました。(笑)
この回向院の報告をした田崎先生ですが、ブラヘイジから2週間近く経っていたせいで、ワードでしか思い出せませんでした。そこで、出て来たワードが、「鼠小僧!!」でした。ブラヘイジに参加した先生は、「あー!」という反応でしたが、参加できず報告を聞いていた先生は「ん?」という反応です。それは、そうですよね。
なぜ、鼠小僧なのでしょうか。それは、回向院には鼠小僧のお墓があるからです。本名は、鼠小僧次郎吉というそうです。時代劇で義賊として活躍する鼠小僧は、大名屋敷から千両箱を盗み、町民の長屋に小判をそっと置いて立ち去ったと言われ、その信仰は江戸時代より盛んでした。その長年捕まらなかった運にあやかろうと、墓石を削りお守りに持つ風習が当時より盛んで、現在も特に受験生が合格祈願に来るそうです。私たちもみんなで、墓石を削って来ました。これまでみんなが削ったため、今の墓石は三代目だそうです。
回向院を後にし、前回報告であった杜子春の碑を通って、勝海舟の生誕の地へと向かいました。今は、生誕跡地として、家族づれで賑わう公園となっています。すると、田崎先生に塾長から、勝海舟は何をやった人?という質問が飛んで来ました。それに対する田崎先生の答えは「西郷隆盛…坂本龍馬」でした。みんな「おー」という反応。勝海舟についてあまり知らない私は、「へぇー(苦笑い)」でした。(笑)そこで、塾長からしっかりとした解説がありましたが、まだ、私もあまり理解してません。
この後は、神田川と隅田川の合流地点を見て、浅草橋へ。そこは造花などの問屋街で、ちょうど入園シーズンだったので、各クラスへ桜の造花を買って帰りました。
以上が、2週に渡った田崎先生によるブラヘイジ報告でした。出張がないため、次の回辺りまで、ブラヘイジ報告が続くかと思います。そして、今回が平成29年度最初の臥竜塾でした。新しい仲間も増え、楽しみになってきました。今年度もどうぞよろしくお願いします。
最後に、メニュー紹介です。今回は、塾長が頂いた国産牛100%のハンバーグ!
そして、昔ながらの日本の洋食屋を意識して、ハンバーグにご飯、味噌汁のセットです。
西村 宗玲