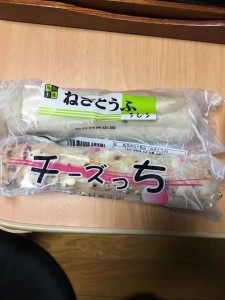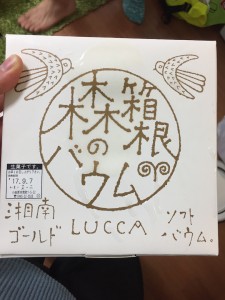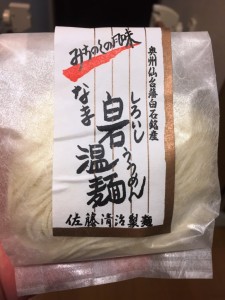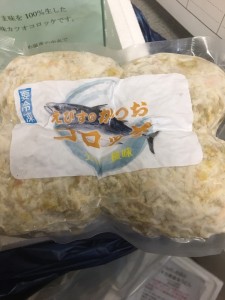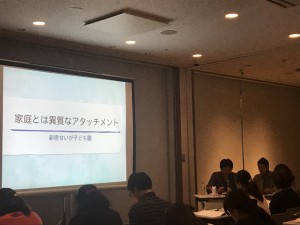大変遅くなって申し訳ありません!
9月5日の報告を完全に忘れていまして、このタイミングになってしまいました。。。
今回は、報告が多い塾となりましたが、その中でも個人的に印象深い報告を報告させていただきます。8月24日(木)から塾長と柿崎先生、森口先生、私で福岡に行ってきまして、その報告をさせていただきました。26、27日の土日はこれまでのドイツツアー参加者による大同窓会が開催されたため、その前に、環境セミナーなどでお世話になっているカグヤさんが、古民家の再生をしているところに宿泊させていただきました。古民家は、福岡県飯塚市にあり、昨年?くらいから再生をしているようです。畳を敷き直したり、壁を塗り直したり、さらには井戸を掘ったりしていて、日本の文化を見直すことができることができます。どこか実家に帰ったような、居心地の良さがあり、落ち着く空間でした。
25日は菅原道真の月命日ということで、古民家の地域の方々に宣伝をして、塾長から「学問」についての講演会が開催されました。学問とは、字のごとく、「問いて学ぶこと」。禅問答などがそうですが、弟子が師匠に問うことが、学びになるというお話をされ、実際に実演をしましょうという流れになりました。もちろん、柿崎先生、森口先生、私の弟子3人から師匠である塾長に質問をして、答えていただきました。
講演会の後は、時間があったので、お礼として井戸掘りのお手伝いです。5メートルくらい地下に穴が掘ってあり、まだ2メートルほど掘らないといけないということで、微力ながらお手伝いしました。大人1人がギリギリ入れる穴で、しゃがむのもやっとの大きさですので、なかなか大変な作業でした、しかし、井戸の中に入る経験は、そうできることではないので、とても楽しく、中はすごく涼しいところでした。しかし、そんな悠長なことは言ってられないくらい、本来の井戸掘りの現場は大変らしく、こんな楽しそうな写真を撮りましたが、本来は違うそうです。
その日は、柿崎先生若林先生が行ったドイツの同窓会だったため、井戸掘りの後は塾長、柿崎先生と森口先生、私の2組に分かれました。柿崎先生の同窓会は北九州で行われ、25日は夜の食事会、26日は午前中、鴨生田保育園さんの見学という流れで行われました。26日は夜、ドイツツアー全参加者による大同窓会があったため、福岡に泊まっていた森口先生と私は夜の大同窓会に間に合うように、車を借りて北九州にお迎えに行き、少し時間があったので、門司港に寄り道し、博多駅まで戻りました。博多駅では、ドイツ大同窓会にサプライズゲストとして参加予定だった、ドイツツアーの通訳である田中さんが待ってくださっており、サプライズ登場の打ち合わせです。
大同窓会は、いつもお世話になっているベルガーさんをお呼びして、研修を行いました。そして、田中さんは大同窓会参加者には、お伝えしてなかったので、驚くような登場をしようという打ち合わせが行われました。サプライズ登場は見事成功し、皆さん田中さんがいらしたことに対して、とても喜んでいただきました。初回のドイツツアーに参加した方は、15年ぶりくらいに、ベルガーさん、田中さんにお会いしたようで、とても楽しい会になりました。
27日は、1日ベルガーさん、塾長、時々田中さんで研修です。午前中はベルガーさんの講演がありましたが、今年のツアーでも話題になった「オープン保育」についてのお話がありました。子どもがどの部屋に行って遊んでもいいというオープン保育ですが、ミュンヘンでも賛否両論あったようです。しかし、最近はオープン保育への理解も深まり、実施する園も増えてきているそうです。
午後は、塾長とベルガーさんによる対談で、時々田中さんにもお話を伺うというスタイルで進んでいきました。そこで、出たキーワードは、「レジリエンス力」です。ベルガーさんは、問題解決能力とおっしゃっていましたが、困難に直面しても自分で解決できる力のことです。レジリエンス力がついている子たちの条件として、3つ挙げられていました。
①誰かに愛されていること②ポジティブ思考③自分が好きなこと
以上の3つがレジリエンス力をつけるのに必要な条件のようです。
では、最後に料理の紹介です。今回は、新宿せいが子ども園の山崎先生のお母様の実家から、塾生へのお礼ということで、鳥取のお魚が届きました。
ねぎとうふ と チーズちくわ
そして、9月1日の31歳の誕生日を迎えた小松崎先生のお祝いをしました。
31歳の誕生日ということで、サーティーワンです!(ダジャレー)
今回は、遅くなりすみませんでした・・・
西村 宗玲